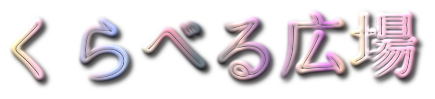ニュースで頻繁に耳にする「衆議院解散」。そのたびに「7条による解散」「首相の専権事項」といった言葉が飛び交いますが、7条解散と69条解散の違いを正確に説明できる方は意外と少ないかもしれません。「七条解散と69条解散の違いは何ですか?」という根本的な疑問を持つ方も多いでしょう。
また、7条解散と69条解散どっちが多いのか、なぜこれほどまでに7条解散が多い理由があるのか、気になるところです。

この記事では、憲法の条文を紐解きながら、7条解散とは?をわかりやすく解説し、対する69条解散とはどのような制度で、過去にどんな事例があったのかを掘り下げます。さらに、それぞれのメリット・デメリット、具体的な7条解散の事例を比較することで、日本の政治の仕組みへの理解を深めます。
- 7条解散と69条解散の根本的な違いと憲法上の根拠
- それぞれの解散がどのような状況で行われるかの具体的な要件
- 「首相の専権事項」と呼ばれるカラクリと、それに対する憲法学上の議論
- 海外の解散制度との比較から見える日本の特徴
本記事の内容
7条解散と69条解散の違いを知る基本
- 7条解散とは?わかりやすく解説
- 69条解散とは?過去の事例
- 七条解散と69条解散の違いは何ですか?
- 憲法7条に基づく解散の根拠
- 憲法69条に基づく解散の要件
- 7条解散のメリット・デメリット
7条解散とは?わかりやすく解説
7条解散とは、一言でいえば「内閣が主導して行う戦略的な解散」のことです。その根拠は、日本国憲法第7条3号にあります。
憲法7条は、天皇が形式的・儀礼的に行う「国事行為」を列挙した条文です。その3号に「衆議院を解散すること」と記されています。しかし、憲法第4条で天皇は「国政に関する権能を有しない」と定められているため、天皇ご自身の政治判断で解散を命じることはありません。
解散の引き金を引くのは、あくまで「内閣の助言と承認」です。つまり、実質的な解散決定権は内閣にあると広く解釈されており、内閣が「今こそ国民の信を問うべきだ」と判断したタイミングで、天皇に解散を助言し、その承認を得て実行されます。
このため、7条解散は内閣支持率が高い時や、重要法案を成立させるための民意の後押しが欲しい時など、時の政権の政治的・戦略的な思惑によって行われるのが大きな特徴です。まさに内閣の「攻め」のカードと言えるでしょう。
7条解散のポイント
- 根拠:憲法第7条3号
- 形式:天皇の国事行為
- 実質:内閣の助言と承認に基づき、内閣が主体的に決定
- 特徴:内閣による政治的・戦略的な判断で行われる「能動的」な解散

69条解散とは?過去の事例
69条解散は、7条解散とは対照的に「衆議院からの不信任に対抗して行われる受動的な解散」です。根拠は日本国憲法第69条にあります。
この条文は、衆議院と内閣の関係性、いわゆる議院内閣制の根幹をなすルールを定めています。具体的には、衆議院で内閣不信任決議案が可決されたり、逆に信任決議案が否決されたりした場合、内閣は国民の代表である衆議院からの信頼を失ったことになります。
その場合、内閣に残された道は2つだけです。
- 10日以内に衆議院を解散して、国民に信を問う
- 内閣総辞職する
つまり、69条解散は、内閣が総辞職を回避するための最後の「対抗措置」として行使するものであり、内閣が自由に時期を選べるものではありません。あくまで衆議院のアクションが起点となる、制約の多い解散です。
69条解散の過去の事例
戦後、この69条解散が行われたのは非常に少なく、以下の4回のみです。
- 1948年(第2次吉田内閣):
GHQの意向も絡み、野党が提出した不信任案が可決。 - 1953年(第4次吉田内閣):
吉田茂首相の「バカヤロー」発言がきっかけで不信任案が可決された「バカヤロー解散」。 - 1980年(第2次大平内閣):
与党・自民党内の反主流派が本会議を欠席したことで不信任案が可決された「ハプニング解散」。 - 1993年(宮沢内閣):
政治改革法案をめぐり、与党・自民党から大量の造反者が出て不信任案が可決。
55年体制崩壊の引き金となった。
69条解散のポイント
これらの事例からもわかるように、69条解散は与党内で深刻な分裂や対立が起きた場合に発生しやすい、政局の大きな転換点となることが多いのが特徴です。
七条解散と69条解散の違いは何ですか?
7条解散と69条解散の最も本質的な違いは、「解散の主導権がどこにあるか」と「そのきっかけ」です。
7条解散は、内閣が主体的・戦略的に「今だ!」と判断して行使する「攻め」の解散です。一方、69条解散は、衆議院から不信任を突きつけられた内閣が、総辞職を避けるために受動的・対抗的に行使する「守り」または「反撃」の解散と言えます。
両者の違いを以下の表に詳しくまとめました。
| 項目 | 7条解散 | 69条解散 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 憲法第7条3号 | 憲法第69条 |
| 解散の主体(形式) | 天皇(国事行為) | 内閣(総辞職の回避) |
| 解散の理由 (きっかけ) | 内閣の高度な政治的判断 (例:重要政策の信を問う、政局の打開) | 衆議院の内閣不信任 (不信任決議可決、または信任決議否決) |
| 実質的な権限 | 内閣(事実上、首相) | 内閣 (ただし、解散か総辞職かの選択に制約される) |
| 性格 | 戦略的・能動的・フリーハンド | 対抗的・受動的・制約的 |

憲法7条に基づく解散の根拠
憲法7条に基づく解散の正当性は、長年、憲法学者の間で議論の対象となってきました。
前述の通り、7条は天皇の国事行為を定めたものであり、解散権そのものを内閣に与える条文ではありません。また、憲法には「内閣はいつでも衆議院を解散できる」とはどこにも書かれていません。この点について、憲法制定に携わったGHQは当初「解散は69条の場合に限定される」との見解を示していました。
しかし、現在の政府や学説の支配的な見解では、7条の冒頭にある「天皇は、内閣の助言と承認により…」という文言を根拠としています。解散という国事行為を行うためには、必ず内閣の「助言と承認」が不可欠であり、この「助言と承認」を行う権限を持つ内閣にこそ、実質的な解散の決定権があると解釈されているのです。
補足:司法の判断を避けた「苫米地事件」判決
1952年の7条解散(抜き打ち解散)を不服とした苫米地義三議員が、解散の無効を訴えた裁判(苫米地事件)がありました。
これに対し、最高裁判所は1960年、「衆議院の解散は、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」であるため、その法律上の有効無効を司法裁判所が審査する権限の外にある、という判断を下しました。これは「統治行為論」と呼ばれ、司法が政治の核心部分への判断を避けた形となりました。
この判決以降、7条解散の合憲性について司法のブレーキがかかることはなくなり、政治の現場では7条解散が慣行として完全に定着することになったのです。
憲法69条に基づく解散の要件
憲法69条に基づく解散は、7条解散とは異なり、議院内閣制の核心をなす、非常に明確で厳格な要件のもとで発動します。
その要件は、以下のいずれかが満たされた場合に限られます。
- 衆議院本会議で内閣不信任の決議案が可決されたとき
- 衆議院本会議で信任の決議案が否決されたとき
このどちらかの事態が発生した瞬間、内閣は「10日以内」という厳格な時間的制約に縛られます。そして、この期間内に「衆議院を解散し、国民の審判を仰ぐ」か「内閣総辞職し、新たな首班を選ぶプロセスに入る」かの二者択一を迫られます。
これは、内閣が行政権を行使する正当性の源泉が、国民の代表である衆議院の信任にある、という議院内閣制の大原則を体現したものです。衆議院から「信任できない」という明確な意思表示をされた以上、内閣はその存立基盤そのものを問われることになるのです。
69条解散の要件と議院内閣制
- 発生条件:
衆議院による明確な不信任の意思表示 - 内閣の選択肢:
10日以内に「解散」か「総辞職」のみ - 憲法上の意義:
内閣の存立が衆議院の信任に基づくという原則の現れ

7条解散のメリット・デメリット
内閣(首相)の強力な権限とされる7条解散ですが、その行使にはメリットと、それを上回るともされるデメリットや問題点が常に指摘されます。
7条解散のメリット
内閣や政治全体にとって、7条解散には以下のような積極的な側面があるとされています。
メリット
- 国民への信を問う機能:
消費税の増税や外交方針の転換など、選挙時の公約になかった重大な政策変更を行う際に、解散を通じて国民の意思を直接問うことができます。 - 政治の膠着状態の打破:
与野党の対立で国会審議が停滞したり、参議院で与党が少数派の「ねじれ国会」で法案が通らなかったりする場合、解散・総選挙で民意を問い、政治状況をリセットする機能があります。 - 政権運営の安定化:
首相が「解散権」というカードを持っていることで、与党内の議員に対する求心力を高め、リーダーシップを発揮しやすくなります。
7条解散のデメリット・問題点
一方で、7条解散には憲法解釈上の問題に加え、民主主義の観点からの深刻なデメリットが指摘されています。
デメリット・問題点
- 解散権の乱用の危険性:
最大のデメリットは、内閣(首相)が、野党の選挙準備が不十分な時や、一時的に内閣支持率が上がった時など、純粋に自党の議席を増やすためだけの「党利党略」で解散権を行使できてしまう点です。 - 憲法上の明確な制約の欠如:
多くの憲法学者は、7条解散が無制約に行使されるべきではないと考えています。
故・芦部信喜教授らが提唱した通説では、解散は「内閣の重要案件が否決された場合」や「新しい重大な政治課題に対処する場合」などに限定されるべきだとされていますが、現実の政治ではこの解釈は機能していません。 - 政治的・経済的コスト:
解散総選挙には約600億円もの国費がかかるとされ、その期間は重要な政策決定が滞る「政治的空白」も生じます。
実際、イギリスでは2011年に「議会任期固定法」を制定し、首相の自由な解散権を封印しました(※同法は2022年に廃止され、再び首相の解散権が復活)。また、ドイツではワイマール憲法の反省から、首相が議会を解散できる要件は極めて厳格に制限されています。日本の7条解散のあり方は、世界的に見ても異例と言えるかもしれません。
7条解散と69条解散の違いと実態
- 7条解散と69条解散どっちが多い?
- なぜ7条解散が多い?その理由とは
- 7条解散の具体的な事例
- 首相の専権事項といわれる背景
- 7条解散と69条解散違いのまとめ
7条解散と69条解散どっちが多い?
これは歴史が明確に示しており、戦後の衆議院解散は比較にならないほど「7条解散」が多いです。
提供されたデータベースの情報(2021年10月14日時点)によると、戦後に行われた25回の衆議院解散のうち、憲法69条(内閣不信任決議の可決)を直接の原因とする解散は、わずか4回です。
残りの21回は、すべて憲法7条に基づく解散となっています。この事実は、日本の政治運営において、内閣、特に首相がいかに大きな主導権を握ってきたかを示唆しています。
なるほど。つまり、日本の政治史は「7条解散の歴史」と言っても過言ではないわけですね。
ちなみに、衆議院議員の任期を4年間全うする「任期満了」に伴う総選挙も、戦後日本では1976年の一度きりです。いかに任期途中の解散が常態化しているかがわかります。

なぜ7条解散が多い?その理由とは
7条解散が圧倒的に多い理由は、それが内閣(首相)にとって極めて強力で使い勝手の良い「政治的武器」だからです。
その背景には、主に2つの要因があります。
7条解散が多用される理由
- 内閣のフリーハンド:
最大の理由は、7条解散には憲法上の明確な制約がないため、内閣が「政治的判断」という名目のもと、事実上いつでも行使できるフリーハンドを持っている点です。
自党に有利な風が吹いた瞬間を狙って選挙を実施できるため、政権維持のための強力なカードとなります。 - 69条の発動ハードルの高さ:
対照的に、69条解散の前提となる「内閣不信任決議の可決」は、非常にハードルが高いです。
通常、与党が衆議院の過半数を握っているため、与党から大規模な造反が起きない限り、野党が提出した不信任案が可決されることはまずありません。
結果として、発動条件が極めて厳しい69条解散は滅多に起こらず、内閣の裁量でいつでも行使できる7条解散が、政局運営の常套手段として定着しているのです。

7条解散の具体的な事例
歴史に残る7条解散には、その時の首相によって象徴的な「通称」が付けられることがよくあります。ここでは代表的な事例を、その背景とともに詳しく見ていきましょう。
郵政解散(2005年・小泉純一郎内閣)
小泉純一郎首相が自身の政治生命を賭けた「郵政民営化関連法案」が、参議院で否決されたことを受けて行われた解散です。衆議院では可決されていましたが、首相は「郵政民営化に賛成か反対か」を唯一の争点として国民に信を問うと宣言。法案に反対した自民党議員の選挙区に「刺客候補」を送り込むなど、劇場型の選挙戦を展開し、歴史的な圧勝を収めました。首相の強いリーダーシップで断行された7条解散の象徴例です。
消費増税解散(2014年・第2次安倍晋三内閣)
2015年10月に予定されていた消費税率10%への引き上げを1年半延期することを決定し、この重大な政策変更について国民の信を問う、という大義名分で行われた解散です。アベノミクスの是非も争点とされました。
国難突破解散(2017年・第3次安倍晋三内閣)
緊迫する北朝鮮情勢や、少子高齢化という「国難」に立ち向かうため、そして消費税増税分の使途を変更して幼児教育無償化などに充てることについて、国民の信を問うとして行われた解散です。しかし、野党からは森友・加計学園問題の追及を逃れるための「自己都合解散」との批判が強く上がりました。
補足:解散の「大義名分」
7条解sanを行う際、首相は国民やメディアに向けて「なぜ今、解散するのか」という理由、いわゆる「大義名分」を説明します。しかし、その大義が正当なものか、それとも政権の都合を優先した党利党略なのかは、常に有権者の厳しい判断に晒されます。

首相の専権事項といわれる背景
「解散は首相の専権事項」という言葉は、日本の政治報道で頻繁に使われる決まり文句です。これは、7条解散の最終的な決定権が、事実上、内閣総理大臣(首相)一人に委ねられているという政治慣行を指します。
しかし、憲法の条文上、解散権はあくまで「内閣」という合議体に属しており、「首相」個人に与えられているわけではありません。では、なぜこのような慣行が生まれたのでしょうか。その鍵は、首相が持つ「国務大臣の任免権」にあります。
「首相の専権事項」が成立するメカニズム
- 閣議は「全員一致」が原則:
内閣の最高意思決定機関である「閣議」は、明治以来の慣行により、全員一致で議決することが原則です。
したがって、解散を閣議決定するには、全閣僚の賛成が必要です。 - 首相は大臣をクビにできる:
しかし、憲法68条は、首相に国務大臣を任命し、そして任意に罷免する(クビにする)権利を保障しています。 - 罷免権を背景にした主導権:
この罷免権があるため、もし閣議で解散に反対する大臣がいたとしても、首相はその大臣を罷免して、自分の意向に従う人物を後任に据えることができます。
これにより、首相は最終的に閣議を全員一致に持ち込むことが理論上可能です。
実際に解散のために大臣が罷免された例は戦後ありませんが、この「罷免権」という強力なカードを持っていること自体が、他の閣僚に対する強い圧力となり、首相の意向を閣議の総意たらしめるのです。
これが、憲法上は「内閣」の権限である解散が、事実上「首相の専権事項」と呼ばれるカラクリです。

7条解散と69条解散違いのまとめ
最後に、この記事で解説してきた「7条解散と69条解散の違い」と、それに関連する重要なポイントを一覧でまとめます。
- 衆議院の解散には、憲法7条と69条に基づく2つのルートが存在する
- 7条解散は、天皇の国事行為として形式的に行われるが、実質的な決定権は内閣にある
- 7条解散は、内閣が政治的・戦略的な判断で、能動的に行使する「攻め」の解散である
- 69条解散は、衆議院で内閣不信任決議が可決された場合に発生する
- 不信任された内閣は、10日以内に「解散」か「総辞職」かの選択を迫られる
- 69条解散は、衆議院の意思表示に対する、受動的・対抗的な「守り」の解散である
- 両者の最大の違いは、解散の「きっかけ」と「主導権」の所在にある
- 戦後の歴史では、解散のほとんど(8割以上)が7条解散であり、69条解散は4回のみ
- 7条解散が多用されるのは、内閣が自由にタイミングを選べる、使い勝手の良い戦略的カードだからである
- 7条解散には、党利党略のために乱用される危険性が常に指摘されている
- 学説上は7条解散にも一定の制約があるべきとされるが、政治の現場では機能していない
- 7条解散が「首相の専権事項」と呼ばれるのは、首相が持つ国務大臣の任免権(罷免権)が背景にあるため
- 首相は罷免権を背景に、解散の閣議決定を主導できる
- 海外では、日本の7条解散のように首相が自由な解散権を持つ例は少なくなっている
- この解散制度のあり方は、日本の議院内閣制の大きな特徴であり、議論の的でもある