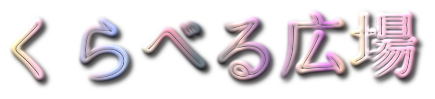ビジネスシーンで頻繁に利用されるメール。
その中でも、宛先を指定する際に目にする「CC」や「BCC」といった項目。
なんとなく使っているけれど、それぞれの機能や使い分けについて、いまいちピンと来ていない方もいるのではないでしょうか。
「メール CC BCC とは一体何なのか」
「CCとBCCはどう使い分けますか」
と疑問に思ったり、BCCを使った際に
「BCC 相手にはどう見えるのだろう」
と不安に感じたことがある方もいるかもしれません。
この記事では、今さら聞けないメールの「CC」「BCC」について、わかりやすく解説します。
「メールでのCCの書き方や返信のやり方」についても触れながら、ビジネスの場でスマートに使いこなせるよう、具体例を交えてご紹介します。
また、「CCとBCCを同時に送るとどうなる?」といった疑問にもお答えし、
ccとbccを使わない方が良いケースについても解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読むと、次のことがわかります。
- CCとBCCの基本的な意味と機能
- CCとBCCの具体的な使い分け方
- BCCでメールを送った際に相手にどのように見えるか
- CCとBCCを同時に使用する際の注意点
本記事の内容
CCBCCの違いとは?ビジネスで役立つ使い分け
- 基本を理解
- どう使い分けますか?具体例を紹介
- BCCは相手にはどう見える?他の受信者への影響
- 同時に送るとどうなる?注意点
- どちらも使わない方が良い場合とは?
基本を理解
メールにおけるCCとBCCは、複数の相手に情報を共有する際に用いられる機能です。
どちらも宛先を増やす目的は同じですが、その仕組みと使い方には明確な違いがあります。
それぞれの特性を理解することで、よりスマートに、かつ安全にメールコミュニケーションを行うことができるでしょう。
まず、CC(Carbon Copy)についてご説明します。
CCは、日本語では「カーボンコピー」と訳されます。
これは、オリジナルの文書の写しを意味し、メールにおいては、送信者と主要な宛先(TO)に加えて、情報共有をしたい相手に同じ内容のメールを送る機能です。
CCに入力されたメールアドレスは、TO、CC、BCCの全ての受信者に公開されます。
そのため、「このメールの内容を、この人にも共有しています」ということを、全員に知らせる意図がある場合に適しています。
例えば、プロジェクトの進捗状況をチームメンバーに共有する際に、リーダーをTOに、その他のメンバーをCCに入れるといった使い方が考えられます。
これにより、リーダーへの報告と同時に、他のメンバーも状況を把握することが可能になります。
次に、BCC(Blind Carbon Copy)についてです。
BCCは、「ブラインドカーボンコピー」と訳されます。
「ブラインド」という言葉が示すように、BCCに入力されたメールアドレスは、他の受信者には一切公開されません。
つまり、TOやCCに入力された相手には、BCCに誰が追加されているのかを知ることができません。
この特性から、BCCは、受信者同士のメールアドレスを互いに知られたくない場合や、一斉送信を行う際に適しています。
例えば、同窓会の案内メールを多数の参加者に送る際に、参加者全員のメールアドレスをBCCに入れることで、プライバシーを保護することができます。
CCとBCCの違いをまとめると、以下の表のようになります。
| 機能 | CC (カーボンコピー) | BCC (ブラインドカーボンコピー) |
|---|---|---|
| 宛先 | 受信者全員に公開 | 送信者のみが把握 |
| 目的 | 情報共有 関係者への周知 | プライバシー保護 一斉送信 |
| 適切な場面 | チーム内での情報共有 上司への報告 | 多数の宛先への一斉送信 個人情報保護 |
このように、CCとBCCは、それぞれ異なる特性を持っています。
メールの内容や目的に応じて、適切な機能を選択することが重要です。
誤った使い方をすると、情報漏洩やマナー違反につながる可能性もあるため、十分に注意しましょう。
どう使い分けますか?具体例を紹介
CCとBCCの使い分けは、メールを送る目的と、受信者間の関係性を考慮して判断することが重要です。
ここでは、具体的な例を交えながら、それぞれの適切な使い方を解説します。
まず、CCを使うべき場面として、以下のようなケースが考えられます。
- 上司への報告:
部下が顧客とのやり取りを上司に報告する際、上司をCCに入れることで、上司は状況を把握し、必要に応じて指示を出すことができます。 - チーム内での情報共有:
プロジェクトメンバー間で情報を共有する際、関係者全員をCCに入れることで、全員が同じ情報を共有し、連携を円滑に進めることができます。 - 議事録の共有:
会議の議事録を参加者全員に共有する際、参加者をCCに入れることで、内容の確認と認識の統一を図ることができます。
一方、BCCを使うべき場面としては、以下のようなケースが考えられます。
- 一斉送信:
多数の顧客や会員にメールを一斉送信する際、受信者同士のメールアドレスを互いに知られたくない場合に、BCCを使用します。 - クレーム対応:
顧客からのクレームに対して、担当者が上司に相談する際、顧客には上司のメールアドレスを知られたくない場合に、上司をBCCに入れることがあります。 - 個人的な連絡:
個人的な知り合いに、他の人に知られたくない情報を送る際に、BCCを使用します。
以下に、CCとBCCの使い分けを具体例を交えてまとめました。
| 場面 | CC | BCC |
|---|---|---|
| プロジェクトの進捗報告 | プロジェクトリーダー 関連部署の担当者 | - |
| 会議の議事録共有 | 会議参加者全員 | - |
| 顧客への新サービス案内 | - | 顧客リスト |
| イベント告知 | - | イベント参加希望者リスト |
| 社内向けアンケート | 回答を集計する担当者 | 従業員リスト |
このように、CCとBCCは、それぞれ異なる場面で有効に活用できます。
大切なのは、それぞれの特性を理解し、状況に応じて適切に使い分けることです。
ただし、BCCの使い方には注意が必要です。
BCCは、相手に隠れて情報を共有する機能であるため、使い方によっては、不信感を与えてしまう可能性があります。
特に、社外の相手とのやり取りでは、BCCの使用は慎重に検討する必要があるでしょう。
BCCは相手にはどう見える?他の受信者への影響
BCCに入力されたメールアドレスは、他の受信者にはどのように見えるのでしょうか。
また、BCCの利用は、他の受信者にどのような影響を与えるのでしょうか。
まず、BCCに入力されたメールアドレスは、TOやCCに入力された受信者には一切表示されません。
受信者は、自分がTOまたはCCに入っていることしか認識できず、他に誰が同じメールを受信しているのかを知ることはできません。
例えば、あなたがTOに指定されたメールを受け取ったとします。
そのメールには、CCに他の人の名前が記載されているかもしれませんが、BCCに誰が指定されているかを知ることはできません。
同様に、あなたがCCに指定されたメールを受け取った場合も、BCCの情報は一切表示されません。
BCCは、あくまで送信者だけが把握できる情報なのです。
次に、BCCの利用が他の受信者に与える影響について考えてみましょう。
BCCは、受信者同士のメールアドレスを互いに知られたくない場合や、一斉送信を行う際に適しています。
しかし、BCCを多用すると、受信者からの信頼を損なう可能性もあるため注意が必要です。
例えば、あなたが顧客からの問い合わせに対応する際、上司に相談するために上司をBCCに入れたとします。
顧客は、あなたが上司に相談していることを知らずに、あなたとのやり取りを進めます。
もし、顧客がその事実を知った場合、「隠れて相談されていた」と感じ、不信感を抱くかもしれません。
また、BCCで一斉送信を行う場合、受信者は自分が特別扱いされていないと感じる可能性があります。
特に、個人的なメッセージや特別なオファーを送る際には、BCCではなく、個別にメールを送る方が、よりパーソナルな印象を与えることができるでしょう。
このように、BCCは、使い方によっては、受信者にネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。
BCCを利用する際には、その目的と、受信者に与える影響を十分に考慮することが重要です。

同時に送るとどうなる?注意点
BCCとCCを同時に使用する場合、それぞれの特性を理解した上で、意図した情報共有とプライバシー保護が実現できているかを確認することが重要です。
まず、技術的な側面から説明すると、BCCとCCを同時に指定して送信されたメールは、それぞれの宛先に意図通りに配信されます。
CC宛の受信者には、TOとCCの宛先が表示され、BCC宛の受信者には、TOとCCの宛先は表示されません。
BCCの受信者には、他のBCCの受信者も表示されません。
しかし、BCCとCCを同時に使用する際には、いくつかの注意点があります。
- 情報共有の範囲:
CCは、宛先を公開して情報共有を行うことを目的としています。
一方、BCCは、宛先を非公開にして情報共有を行うことを目的としています。
そのため、CCとBCCを同時に使用する場合は、誰にどこまで情報を共有したいのかを明確にする必要があります。
- 返信時の注意:
CCに入っている受信者が「全員に返信」を選択した場合、BCCに入っている受信者にも返信が届いてしまいます。
BCCに入っている受信者は、自分がBCCに入っていることを知られたくない場合もあるため、注意が必要です。
- 誤送信のリスク:
BCCに入れるべき宛先を誤ってCCに入れてしまうと、メールアドレスが公開されてしまう可能性があります。
特に、個人情報を含むメールを送る場合は、十分に注意する必要があります。
以下に、BCCとCCを同時に使用する際の注意点をまとめました。
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 情報共有の範囲 | CCとBCCの目的を理解し、 誰にどこまで情報を共有したいのかを明確にする |
| 返信時の注意 | CCの受信者が「全員に返信」を選択した場合、 BCCの受信者にも返信が届く可能性がある |
| 誤送信のリスク | BCCに入れるべき宛先を誤ってCCに入れないように注意する |
このように、BCCとCCを同時に使用する場合は、それぞれの特性と注意点を理解した上で、慎重に判断する必要があります。
どちらも使わない方が良い場合とは?
CCとBCCは便利な機能ですが、状況によっては、どちらも使わない方が良い場合があります。
ここでは、その具体的なケースと理由を解説します。
まず、CCとBCCのどちらも使わない方が良いケースとして、以下のような状況が考えられます。
- 個人的なやり取り:
友人や家族との個人的なやり取りでは、CCやBCCを使う必要はほとんどありません。
個人的なメールは、通常、特定の相手に宛てて送られるものであり、他の人に共有する必要がないためです。
- 返信が不要な連絡:
単なる連絡事項や、返信を期待しないお知らせを送る場合も、CCやBCCを使う必要はありません。
例えば、イベントの日時や場所を伝えるだけのメールであれば、TOに宛先を入力して送るだけで十分です。
- 機密情報を含むメール:
機密情報を含むメールを送る場合は、CCやBCCを使うべきではありません。
CCを使うと、宛先が公開されてしまい、情報漏洩のリスクが高まります。
BCCを使った場合でも、誤送信のリスクがあるため、機密情報のメールは、暗号化するなど、より安全な方法で送るべきです。
- 大人数への一斉送信:
数百人、数千人といった大人数にメールを送る場合は、CCやBCCを使うべきではありません。
CCを使うと、受信者のメールソフトに負荷がかかり、受信に時間がかかったり、エラーが発生したりする可能性があります。
BCCを使った場合でも、大量のメールを送信すると、迷惑メールと判断される可能性があり、受信者に届かないことがあります。
大人数にメールを送る場合は、メール配信システムを利用するなど、適切な方法を選択する必要があります。
このように、CCとBCCは便利な機能ではありますが、状況によっては、使わない方が良い場合があります。
メールを送る際には、その目的と内容を考慮し、適切な方法を選択することが重要です。
もう迷わない!メールのCCBCCの違いと正しい使い方
- CCを使う際の注意点|プライバシーとマナー
- BCCを使うリスク|情報漏洩と誤送信
- メールでのCCの書き方と返信のやり方:状況別の対応
- CCの受信者に返信義務はある?
- 宛先が多い時の対応

CCを使う際の注意点|プライバシーとマナー
CC(カーボンコピー)は、情報を共有するために便利な機能ですが、使用する際にはいくつかの注意点があります。
特に、プライバシーとマナーの観点から、慎重な判断が求められます。
まず、CCを使う上で最も重要なことは、宛先を公開することへの意識です。
CCに入力されたメールアドレスは、TO(宛先)、CC、BCCの全ての受信者に公開されます。
そのため、受信者同士が面識のない場合や、メールアドレスを知られたくない相手が含まれる場合は、CCの使用を避けるべきです。
例えば、社外の顧客リストをCCに入れて一斉送信した場合、顧客のメールアドレスが他の顧客に公開されてしまい、個人情報保護の観点から問題となる可能性があります。
このような場合は、BCC(ブラインドカーボンコピー)を使用することで、受信者のメールアドレスを非公開にすることができます。
次に、CCを使う際には、受信者の負担を考慮することも大切です。
CCに多くの人を指定すると、受信者のメールボックスが不要な情報で溢れかえり、重要なメールを見落としてしまう可能性があります。
そのため、CCに入れるべきかどうか迷った場合は、本当に情報共有が必要な相手なのかを慎重に検討し、必要最小限の人数に絞るようにしましょう。
また、CCでメールを受信した場合、原則として返信は不要です。
CCは、あくまで情報共有を目的とした機能であり、返信を期待するものではありません。
ただし、メールの内容によっては、返信が必要な場合もあります。
例えば、CCで送られてきた議事録に誤りがあった場合や、確認を求められた場合は、速やかに返信するようにしましょう。
以下に、CCを使う際の注意点をまとめました。
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| プライバシー | 受信者同士が面識のない場合や、 メールアドレスを知られたくない相手が含まれる場合は、CCの使用を避ける |
| 受信者の負担 | CCに入れる人数は必要最小限に絞り、 受信者のメールボックスが不要な情報で溢れかえらないように配慮する |
| 返信の要否 | CCでメールを受信した場合、原則として返信は不要。 ただし、メールの内容によっては、返信が必要な場合もある |
| 宛名の記載 | 誰に宛てたメールなのかを明確にするため、 TOの宛名に加えて、CCの宛名も記載する |
これらの注意点を守ることで、CCをより効果的に活用し、スムーズなコミュニケーションを実現することができます。
BCCを使うリスク|情報漏洩と誤送信
BCC(ブラインドカーボンコピー)は、受信者のメールアドレスを非公開にするという点で、非常に便利な機能です。
しかし、その利便性の裏には、いくつかのリスクが潜んでいます。
特に、情報漏洩と誤送信のリスクは、BCCを使う上で常に意識しておくべき重要な点です。
まず、情報漏洩のリスクについてです。
BCCは、受信者のメールアドレスを非公開にする機能ですが、送信者が誤ってCCにメールアドレスを入力してしまった場合、その情報は公開されてしまいます。
例えば、顧客リストをBCCに入れるつもりが、誤ってCCに入れて送信してしまった場合、顧客のメールアドレスが他の顧客に公開されてしまい、個人情報保護法に違反する可能性があります。
また、BCCで送信したメールが、受信者によって転送された場合、転送先の相手には、BCCに入っていたメールアドレスは表示されませんが、元のメールにBCCの宛先が含まれていたことが分かってしまいます。
次に、誤送信のリスクについてです。
BCCは、送信者が宛先を間違えてしまうと、取り返しがつかない事態に陥る可能性があります。
例えば、本来送るべきでない相手に、誤ってBCCでメールを送ってしまった場合、そのメールの内容が機密情報であれば、情報漏洩につながる可能性があります。
また、BCCで送信したメールに、誤った情報が含まれていた場合、訂正メールを送ることが難しくなります。
なぜなら、BCCの受信者は、自分がBCCに入っていることを知られたくない場合もあるため、訂正メールを送ることで、その事実を知られてしまう可能性があるからです。
以下に、BCCを使う際のリスクをまとめました。
| リスク | 詳細 |
|---|---|
| 情報漏洩 | 送信者が誤ってCCにメールアドレスを入力した場合、 その情報が公開されてしまう |
| 誤送信 | 送信者が宛先を間違えてしまうと、 取り返しがつかない事態に陥る可能性がある |
| 転送による情報漏洩 | 受信者によって転送された場合、 元のメールにBCCの宛先が含まれていたことが分かってしまう |
| 訂正メールの困難さ | BCCで送信したメールに誤りがあった場合、 訂正メールを送ることが難しくなる |
これらのリスクを回避するためには、BCCを使う際には、以下の点に注意することが重要です。
- 宛先を慎重に確認する
- 送信前に、内容に誤りがないかを確認する
- 機密情報を含むメールは、BCCを使わない
- BCCを使う必要性を慎重に検討する
これらの注意点を守ることで、BCCのリスクを最小限に抑え、安全に活用することができます。
メールでのCCの書き方と返信のやり方:状況別の対応
CC(カーボンコピー)は、ビジネスメールにおいて、情報を共有するために頻繁に使用される機能です。
しかし、その書き方や返信のやり方には、一定のマナーが存在します。
ここでは、状況別にCCの書き方と返信のやり方を解説します。
まず、CCの書き方についてです。
メールを作成する際、CCに宛先を入力するだけでなく、本文にもCCに入れた相手の名前を記載することが望ましいです。
例えば、以下のように記載します。
〇〇様
いつもお世話になっております。
(CC:△△様)
××の件、承知いたしました。このように記載することで、誰に宛てたメールなのか、誰が情報共有されているのかが明確になり、受信者にとって分かりやすくなります。
次に、返信のやり方についてです。
CCでメールを受信した場合、原則として返信は不要です。
CCは、あくまで情報共有を目的とした機能であり、返信を期待するものではありません。
ただし、メールの内容によっては、返信が必要な場合もあります。
例えば、CCで送られてきた議事録に誤りがあった場合や、確認を求められた場合は、速やかに返信するようにしましょう。
返信する際には、以下の点に注意することが大切です。
- 返信する相手:
基本的には、送信者のみに返信します。
ただし、全員に共有すべき情報である場合は、「全員に返信」を選択します。 - 件名:
件名は、原則として変更しません。
ただし、返信の内容が元のメールと大きく異なる場合は、件名を変更しても構いません。 - 引用:
返信する際には、元のメールを引用します。
ただし、引用部分が長すぎる場合は、必要な部分のみを引用するようにしましょう。
以下に、状況別のCCの書き方と返信のやり方をまとめました。
| 状況 | CCの書き方 | 返信のやり方 |
|---|---|---|
| メール作成時 | 本文にCCに入れた相手の名前を記載する | - |
| CCでメールを受信した場合 | 原則として返信は不要 | - |
| 議事録に誤りがあった場合 | 本文にCCに入れた相手の名前を記載する | 送信者のみに返信する |
| 確認を求められた場合 | 本文にCCに入れた相手の名前を記載する | 全員に返信する |
これらのポイントを踏まえることで、CCをより効果的に活用し、円滑なコミュニケーションを実現することができます。
CCの受信者に返信義務はある?
CC(カーボンコピー)でメールを受信した場合、受信者に返信義務はあるのでしょうか。
この点は、ビジネスメールのマナーとして、多くの人が疑問に思うところでしょう。
結論から言うと、CCでメールを受信した場合、原則として返信義務はありません。
CCは、あくまで情報共有を目的とした機能であり、返信を期待するものではありません。
TO(宛先)に指定された人が、そのメールに対して対応することが前提となっているため、CCの受信者が返信してしまうと、情報が錯綜し、混乱を招く可能性があります。
例えば、プロジェクトの進捗報告メールで、リーダーがTOに、メンバーがCCに入っている場合、リーダーが報告内容を確認し、必要に応じて指示を出すことが期待されます。
メンバーがCCでメールを受信した場合、特に指示がない限り、返信する必要はありません。
ただし、例外的に、CCの受信者に返信義務が生じるケースもあります。
- 確認を求められた場合:
送信者から、CCの受信者に対して、確認や承認を求められた場合は、速やかに返信する必要があります。 - 誤りを発見した場合:
CCで送られてきたメールの内容に誤りがあった場合、訂正するために返信する必要があります。 - 意見を求められた場合:
送信者から、CCの受信者に対して、意見や提案を求められた場合は、積極的に返信することが望ましいです。
以下に、CCの受信者に返信義務があるかどうかをまとめました。
| 状況 | 返信義務 |
|---|---|
| 原則 | なし |
| 確認を求められた場合 | あり |
| 誤りを発見した場合 | あり |
| 意見を求められた場合 | 状況による |
このように、CCの受信者に返信義務は原則としてありませんが、状況によっては、返信が必要となる場合もあります。
メールの内容をよく確認し、適切な対応を心がけることが大切です。
宛先が多い時の対応
CC(カーボンコピー)の宛先が多い場合、受信者にとってメールが見づらくなったり、重要な情報が埋もれてしまったりする可能性があります。
そのため、CCの宛先が多い場合は、いくつかの点に注意して対応する必要があります。
まず、CCの宛先を整理することが大切です。
本当にそのメールを共有する必要があるのか、受信者にとって有益な情報なのかを慎重に検討し、CCに入れるべきかどうかを判断しましょう。
例えば、プロジェクトの進捗報告メールで、直接関係のない部署の担当者をCCに入れる必要はありません。
次に、メールの構成を工夫することが重要です。
CCの宛先が多い場合は、メールの冒頭に、宛先(TO)、CC、BCCを明記することで、誰に宛てたメールなのか、誰が情報共有されているのかを明確にすることができます。
また、メールの内容を簡潔にまとめ、重要な情報を強調することで、受信者がメールの内容を理解しやすくなります。
さらに、ファイル共有リンクを活用することも有効です。
メールに直接ファイルを添付するのではなく、ファイル共有サービスを利用して、ファイルのリンクをメールに記載することで、メールの容量を減らし、受信者のメールソフトへの負荷を軽減することができます。
最後に、メール配信システムの利用を検討することもおすすめです。
メール配信システムは、大量の宛先にメールを送信する際に、宛先を管理したり、配信状況を把握したりするのに役立ちます。
CCの宛先が多い場合は、メール配信システムを利用することで、より効率的に、かつ安全にメールを送信することができます。
以下に、CCの宛先が多い時の対応策をまとめました。
| 対応策 | 詳細 |
|---|---|
| CCの宛先の整理 | 本当にそのメールを共有する必要があるのか、 受信者にとって有益な情報なのかを慎重に検討する |
| メール構成の工夫 | 宛先(TO)、CC、BCCを明記し、メールの内容を簡潔にまとめ、 重要な情報を強調する |
| ファイル共有リンクの活用 | ファイル共有サービスを利用して、 ファイルのリンクをメールに記載する |
| メール配信システムの利用 | 大量の宛先にメールを送信する際に、宛先を管理したり、 配信状況を把握したりするのに役立つ |
これらの対応策を参考に、CCの宛先が多い場合でも、受信者にとって分かりやすく、有益なメールを作成するように心がけましょう。
ccbccの違いを理解するための記事内容まとめ
次のように記事の内容をまとめました。
- CCとBCCはメールで複数人に情報を共有する機能である
- CCはカーボンコピーの略
- BCCはブラインドカーボンコピーの略
- CCでは受信者全員に宛先が公開される
- BCCでは送信者のみが宛先を把握する
- CCは情報共有や関係者への周知に適している
- BCCはプライバシー保護や一斉送信に適している
- CCはチーム内共有や上司への報告に役立つ
- BCCは顧客への一斉案内や個人的な連絡に役立つ
- CCとBCCの使い分けはメールの目的と受信者間の関係性を考慮する
- 上司への報告にはCCが適している
- 顧客への一斉送信にはBCCが適している
- BCC利用は信頼を損なう可能性があるため注意が必要だ
- CCとBCCを同時に使う場合は情報共有範囲を明確にする
- 機密情報を含むメールではCCとBCCの使用は避けるべきだ