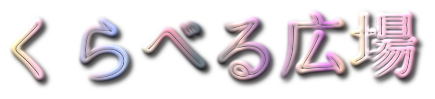一時払い終身保険を活用した相続税対策について、様々な情報を比較検討されている方も多いのではないでしょうか。
相続税の負担軽減や円満な資産承継の手段として、一時払い終身保険は確かに注目されています。
一時払終身保険を相続に利用するメリットは多く、おすすめされる場面も少なくありません。
しかし、メリットだけでなく、相続税対策として生命保険を利用する際のデメリットや、一時払い終身保険ならではの注意点も存在します。
この記事では、一時払い終身保険が相続対策として有効な理由、具体的に一時払い終身保険はどんな人におすすめですかという疑問への回答、そして見落としがちな注意点まで、わかりやすく解説していきます。
一時払い終身保険による相続対策を深く理解し、ご自身にとって最適な選択をするための一助となれば幸いです。
記事のポイントです。
- 一時払い終身保険が相続税対策に有効な理由と具体的なメリット
- どのような人が一時払い終身保険の活用に向いているか
- 一時払い終身保険を利用する際の注意点やデメリット、税金の違い
- 商品を選ぶ際の比較ポイント(返戻率、シミュレーション、ランキング等)

本記事の内容
一時払い 終身保険 の 相続税対策 比較 :メリットと選び方
- 相続に利用するメリットは?
- どんな人におすすめですか?
- おすすめポイント
- シミュレーションで効果検証
- 効果的な生命保険ランキング
相続に利用するメリットは?
一時払い終身保険を相続対策に活用することには、複数の大きなメリットが存在します。
まず、最大の利点として挙げられるのは、生命保険の死亡保険金に設けられている非課税枠を利用できる点でしょう。
被相続人が保険料を負担し、法定相続人が死亡保険金を受け取る場合、「500万円 × 法定相続人の数」で計算される金額までは相続税がかかりません。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人いるケースでは、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税となります。
これは、相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)とは別枠で適用されるため、現預金でそのままのこすよりも相続税の負担を軽減できる可能性が高まります。
次に、死亡保険金は原則として受取人固有の財産とみなされる点も、重要なメリットと言えるでしょう。
そのため、遺産分割協議の対象外となり、他の相続人の同意なしに、受取人が比較的速やかに保険金を受け取ることが可能です。
相続が発生すると、亡くなった方の預金口座は凍結されてしまうため、葬儀費用や当面の生活費、納税資金の準備に困るケースも少なくありません。
しかし、生命保険金であれば、手続き後スムーズに現金で受け取れるため、これらの資金需要に柔軟に対応できます。
さらに、不動産など分割しにくい財産が多い場合に、代償分割の原資としても活用できます。
例えば、長男が実家の土地建物を相続する代わりに、他の兄弟に相応の現金を支払うといったケースで、この保険金が役立ちます。
加えて、保険契約時に受取人を指定できるため、遺言のように「特定の人に確実に財産をのこしたい」という想いを実現する手段にもなり得ます。
これらの理由から、一時払い終身保険は有効な相続対策の一つとして考えられています。

どんな人におすすめですか?
一時払い終身保険は、特に特定の状況やニーズを持つ方々にとって、有効な相続対策の選択肢となり得ます。
まず、相続財産の中に現預金の占める割合が高く、その評価額を圧縮したいと考えている方におすすめできます。
前述の通り、生命保険金には非課税枠があるため、現預金の一部を一時払い終身保険に換えることで、相続税の課税対象となる財産を減らす効果が期待できます。
また、相続税の納税資金を確実に準備しておきたいという方にも適しています。
相続税は原則として相続開始後10ヶ月以内に現金で一括納付する必要があるため、特に不動産など換金性の低い資産が多い場合、納税資金の確保が課題となることがあります。
一時払い終身保険であれば、受取人がスムーズに現金を受け取れるため、納税資金に充当することが可能です。
さらに、特定の相続人に財産を確実にのこしたいと考えている方にも有効な手段と言えるでしょう。
例えば、長年にわたり介護でお世話になった子どもや、事業を継承する後継者など、特定の人へ他の相続財産とは別にまとまった資金をのこしたい場合に活用できます。
保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の影響を受けずに、指定した人へ確実に渡すことが可能です。
加えて、比較的高齢になってから相続対策を検討し始めた方にも、一時払い終身保険は選択肢の一つとなります。
保険商品によっては、80歳以上、あるいは90歳といった高齢でも加入できるものがあり、健康状態に関する告知が比較的緩やかな商品も存在します。
生前贈与のように時間をかけて行う対策が難しい場合でも、一時払い終身保険であれば契約時にまとまった資金を投入することで、短期間で相続対策の効果を得ることが期待できるでしょう。
遺産分割における相続人間のトラブルを未然に防ぎたいと考える方にとっても、受取人が明確で分割の必要がない保険金は、有効な対策となりえます。
ただし、加入にはまとまった資金が必要となる点や、早期に解約すると元本割れするリスクがある点には留意が必要です。
おすすめポイント
相続対策として一時払い終身保険を検討する際、いくつかのおすすめポイント、つまり特に注目すべき利点があります。
繰り返しになりますが、最も重要なポイントは「死亡保険金の非課税枠」を効果的に活用できる点です。
「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠は、相続税の基礎控除とは別に設けられているため、これを最大限に生かすことで相続税負担の軽減につながります。
相続財産が現金や預貯金中心である場合、この非課税枠を利用しない手はありません。
次に、「受取人指定による確実な資産承継」も大きなメリットです。
保険契約時に受取人を指定することで、被相続人の意思に基づき、特定の人へ確実に財産をのこすことができます。
これは遺言と同様の効果を持ちながら、遺産分割協議を経ずに手続きを進められる点が異なります。
相続人間の無用な争いを避けたい場合や、特定の人への感謝の気持ちを形にしたい場合に有効な手段となるでしょう。
また、「現金化の早さ」も実用的なおすすめポイントと言えます。
相続発生後、預金口座は凍結される可能性がありますが、死亡保険金は請求手続き後、比較的短期間で現金として支払われます。
これにより、葬儀費用や当面の生活費、そして期限のある相続税の納税資金などをスムーズに準備することが可能になります。
流動性の高い資産を確保できる点は、のこされた家族にとって大きな安心材料となるはずです。
さらに、「加入のしやすさ」、特に高齢者でも加入しやすい商品が多い点も魅力です。
相続対策は早めに始めるに越したことはありませんが、様々な事情で高齢になってから検討を開始するケースも少なくありません。
一時払い終身保険には、告知項目が少ない、あるいは健康状態に関する告知が不要な商品もあり、持病がある方や高齢の方でも加入できる可能性が残されています。
これらのポイントを踏まえると、一時払い終身保険は、相続税の節税、円満な資産承継、そして納税資金の確保という複数の目的を達成するための有効なツールとしておすすめできるのです。

シミュレーションで効果検証
一時払い終身保険が相続対策に有効であるかを具体的に判断するには、シミュレーションによる効果検証が非常に重要となります。
なぜなら、節税効果は、個々の家族構成や相続財産の総額、そして保険の加入状況によって大きく異なるからです。
机上の空論ではなく、ご自身の状況に近い形で試算してみることで、加入のメリットをより明確に把握できます。
シミュレーションを行うことで、まず、一時払い終身保険に加入した場合としなかった場合の相続税額の差を具体的に比較することが可能です。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人(計3人)、相続財産が1億円(すべて現預金)というケースを考えてみましょう。
この場合、相続税の基礎控除額は3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円です。
もし保険に加入していなければ、課税遺産総額は1億円 - 4,800万円 = 5,200万円となります(配偶者控除等は考慮せず)。
一方、法定相続人が3人なので、生命保険の非課税枠は500万円 × 3人 = 1,500万円です。
仮に、現預金のうち1,500万円を使って一時払い終身保険(死亡保険金1,500万円と仮定)に加入したとします。
すると、相続財産は現金8,500万円と死亡保険金1,500万円の合計1億円ですが、保険金1,500万円は非課税枠内なので、課税対象となるのは現金8,500万円のみとなります。
この場合の課税遺産総額は8,500万円 - 4,800万円 = 3,700万円となり、加入しなかった場合と比較して課税遺産総額を1,500万円圧縮できたことになります。
このように、具体的な数字で比較することで、非課税枠の効果を実感しやすくなります。
また、シミュレーションを通じて、生命保険の非課税枠と相続税の基礎控除の関係性についても理解が深まるでしょう。
どれくらいの保険金額が自身の相続対策にとって最適なのかを検討する上でも、試算は欠かせません。
ただし、注意点として、ここでのシミュレーションは簡略化したものであり、実際の相続税計算はさらに複雑な要素(配偶者の税額軽減、各種控除、財産の評価方法など)が絡んできます。
したがって、詳細なシミュレーションや具体的なプランニングについては、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家へ相談することが最も確実な方法と言えます。
効果的な生命保険ランキング
相続税対策を目的として生命保険を選ぶ際、様々な商品が比較検討の対象となり、ランキング形式で紹介されることも多くあります。
ランキングを参考にすることで、現在どのような保険商品が注目されているのか、その特徴を効率的に把握する手助けになります。
相続税対策としてランキング上位によく登場するのは、やはり一時払い終身保険です。
その理由は、これまで述べてきたように、死亡保険金の非課税枠を即効性をもって活用できる点、高齢でも加入しやすい点、受取人指定による確実な資産承継が可能である点などが挙げられます。
まとまった資金を一度に投入することで、短期間で相続財産の評価額を圧縮したいというニーズに合致しやすいのです。
しかし、一時払い終身保険以外にも、相続対策として有効と考えられる生命保険は存在します。
例えば、通常の終身保険(月払いや年払い)も、長期間にわたって保険料を払い込むことで、結果的に死亡保険金の非課税枠を活用できます。
また、保険会社によっては、相続対策に特化した設計の商品や、持病があっても加入しやすい引受基準緩和型の終身保険なども提供されています。
ランキングでは、これらの保険商品の特徴、例えば返戻率の高さ、保障内容、加入可能年齢、告知条件の緩やかさなどが比較されていることが多いでしょう。
特に、外貨建ての一時払い終身保険などは、円建てに比べて高い利回りが期待できる反面、為替リスクも伴うため、その特性を理解した上で検討する必要があります。
ランキング情報を参考にする際の注意点としては、まず情報の新しさを確認することが重要です。
保険商品は常に改定されており、金利情勢によっても内容は変動します。
また、どのような基準(例:申込数、返戻率、保障内容)で作成されたランキングなのかを把握することも大切です。
最終的には、ランキングはあくまで参考情報の一つと捉え、ご自身の年齢、健康状態、資産状況、そして相続に対する考え方に最も適した保険商品を、専門家のアドバイスも得ながら慎重に選ぶことが何よりも重要と言えます。

一時払い 終身保険 の 相続税対策 比較 :注意点と商品選び
- 注意点は?税金の違いも解説
- 生命保険のデメリットも理解しよう
- 返戻率をチェック
- 80歳以上からの加入の可能性
- 人気ランキングの活用
- 一番人気なのは?商品の特徴
注意点は?税金の違いも解説
一時払い終身保険は相続対策に有効な手段となり得ますが、加入を検討する際にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。
また、契約形態によってかかる税金の種類が異なる点も重要なポイントです。
まず、最も基本的な注意点として、加入時にまとまった資金が必要になることが挙げられます。
保険料を一括で支払うため、手元の資金に余裕がない場合は加入が難しいかもしれません。
生活資金などを圧迫しないよう、余裕資金の範囲内で検討することが大切です。
次に、早期に解約した場合、解約返戻金が払い込んだ保険料を下回る、いわゆる元本割れのリスクがある点も認識しておきましょう。
一時払い終身保険は長期的な運用を前提としている商品が多いため、急な資金需要が発生する可能性も考慮し、慎重に判断する必要があります。
さらに、税制面での注意点として、所得税や住民税の計算時に適用される生命保険料控除は、保険料を支払った年の一度しか利用できないという点があります。
月払いや年払いの場合は毎年控除を受けられますが、一時払いはそのメリットを享受できる期間が限られます。
加えて、インフレーションによって、将来受け取る保険金の実質的な価値が目減りしてしまうリスクも考慮すべきでしょう。
契約時に定められた保険金額は、物価上昇に合わせて増額されるわけではありません。
そして、最も重要な注意点の一つが、保険契約の関係性(契約者、被保険者、保険金受取人)によって、死亡保険金にかかる税金の種類が変わることです。
相続税対策として活用する場合は、契約者と被保険者を同一人物(例:父)とし、保険金受取人を法定相続人(例:妻や子)とする契約形態にする必要があります。
この場合に限り、死亡保険金が相続税の対象となり、非課税枠の適用を受けられます。
もし、契約者(例:父)と保険金受取人(例:父)が同一で、被保険者が異なる(例:母)場合は、保険金は一時所得として所得税・住民税の対象となります。
また、契約者(例:父)、被保険者(例:母)、保険金受取人(例:子)がすべて異なる場合は、保険金は贈与税の対象となります。
贈与税は一般的に税負担が重くなる傾向があるため、契約時にはこの関係性を十分に確認し、目的に合った契約形態を選ぶことが極めて重要です。

生命保険のデメリットも理解しよう
生命保険は有効な相続税対策のツールとなり得ますが、メリットばかりではありません。
加入を検討する際には、デメリットや潜在的なリスクについても十分に理解しておくことが不可欠です。
まず、生命保険に加入するには当然ながら保険料の負担が発生します。
特に一時払い終身保険の場合は、まとまった資金が必要となるため、手元の流動性を低下させる可能性があります。
他の資産運用や、不測の事態に備えるための資金とのバランスを考える必要があるでしょう。
次に、前述の通り、保険商品を途中で解約する場合、払い込んだ保険料を下回る金額しか戻ってこない「元本割れ」のリスクがあります。
特に加入後、短期間での解約は損失が発生する可能性が高まります。
長期的な視点で、解約せずに継続できるかどうかを慎重に見極めることが重要です。
また、インフレーションのリスクも無視できません。
長期間にわたる保険契約の場合、契約時に設定した保険金額が、将来の物価上昇によって実質的な価値を失ってしまう可能性があります。
特に固定金利型の保険商品の場合、このリスクはより顕著になります。
さらに、死亡保険金の受取人を誰にするかによっては、相続人間でのトラブルの原因となる可能性もゼロではありません。
原則として保険金は受取人固有の財産ですが、他の相続財産とのバランスが著しく不公平であると判断された場合、特別受益とみなされ、遺留分侵害額請求の対象となる可能性も指摘されています。
受取人の指定は慎重に行うべきです。
加えて、保険会社が経営破綻するリスクも考慮に入れる必要があります。
万が一、保険会社が破綻した場合でも、生命保険契約者保護機構によって一定の範囲で契約は保護されますが、保険金額や解約返戻金が削減される可能性は否定できません。
保険会社の財務健全性なども確認しておくとよいでしょう。
これらのデメリットを理解した上で、生命保険がご自身の相続対策の目的に本当に合致しているのか、他の対策(生前贈与、不動産活用など)と比較検討し、総合的に判断することが求められます。

返戻率をチェック
一時払い終身保険を比較検討する上で、重要な指標の一つとなるのが「返戻率」です。
返戻率とは、払い込んだ保険料の総額に対して、将来受け取れる解約返戻金や死亡保険金がどれくらいの割合になるかを示す数値のことです。
この数値を確認することで、保険の貯蓄性や運用効率をある程度把握することができます。
一時払い終身保険の返戻率は、一般的に月払いや年払いの終身保険と比較して高くなる傾向があります。
これは、保険会社が契約時にまとまった保険料を受け取ることで、より長期間、安定した運用を行うことが可能になるためです。
返戻率を比較する際には、いくつかのポイントに注意する必要があります。
まず、返戻率は保険契約の経過年数によって変動する点です。
通常、契約から年数が経過するほど返戻率は上昇していきます。
比較する際は、特定の時点(例えば、10年後、20年後、あるいは平均寿命に近い年齢など)での返戻率を確認するとよいでしょう。
特に、解約を視野に入れる場合は、解約返戻金が払い込んだ保険料を上回る(返戻率が100%を超える)のがいつ頃になるのかを把握しておくことが重要です。
次に、円建ての保険か、外貨建ての保険かによっても返戻率の考え方が異なります。
外貨建て保険は、円建てに比べて高い予定利率が設定されていることが多く、一見すると返戻率が高く見えます。
しかし、為替レートの変動によって、円換算した際の受取額が大きく変わるリスク(為替リスク)が伴います。
為替手数料などのコストも考慮する必要があるため、表面的な返戻率だけで判断するのは避けるべきです。
さらに、保険会社や商品設計によっても返戻率は異なります。
各社のパンフレットや設計書を取り寄せ、同じ条件(契約年齢、性別、保険金額など)で返戻率を比較検討することが大切です。
なお、「解約返戻金」の返戻率と、「死亡保険金」の返戻率は異なる場合が多い点にも留意が必要です。
相続対策を主目的とする場合は、死亡保険金の返戻率を重視することになります。
返戻率は保険商品を選ぶ上での重要な判断材料の一つですが、保障内容や加入条件、保険会社の信頼性なども含めて、総合的に比較検討することをおすすめします。

80歳以上からの加入の可能性
相続対策を考え始める時期は人それぞれですが、比較的高齢になってから検討を開始する方も少なくありません。
そのような方々にとって、一時払い終身保険は有力な選択肢の一つとなり得ます。
その理由として、一時払い終身保険には80歳以上、場合によっては90歳まで加入申し込みが可能な商品が存在することが挙げられます。
一般的な生命保険は、加入できる年齢に上限が設けられており、高齢になると加入が難しくなるケースが多いです。
しかし、一時払い終身保険の中には、高齢者を対象とした商品設計がなされているものがあります。
なぜ高齢でも加入しやすいのかというと、健康状態に関する告知条件が通常の保険よりも緩やかに設定されている場合が多いからです。
商品によっては、簡単な告知項目(例:現在入院中か、過去一定期間内に手術や入院をすすめられたことがあるか等)に該当しなければ加入できる「引受基準緩和型」や、告知そのものが不要な「無選択型」「無告知型」と呼ばれるタイプもあります。
もちろん、告知が緩やかである分、保険料が割高に設定されていたり、加入後一定期間(例:1~2年)内に死亡した場合の保険金が削減されたりするなどの制約がある場合もあります。
80歳以上の方が一時払い終身保険への加入を検討する際には、いくつかの点に注意が必要です。
まず、選択できる商品の種類が、若い年齢層に比べて限られる可能性があります。
また、高齢での加入は、一般的に保険料が高くなる傾向にあります。
さらに、加入目的を明確にしておくことが重要です。
相続税対策なのか、納税資金の確保なのか、特定の相続人への資産承継なのか、目的によって最適な保険金額や商品設計は異なります。
とはいえ、高齢であることを理由に相続対策を諦める必要はありません。
一時払い終身保険を活用することで、晩年からでも、生命保険の非課税枠を利用した相続税対策や、円満な資産承継の準備を進めることが可能になります。
ご自身の健康状態や資産状況に合わせて、無理のない範囲で検討してみる価値はあるでしょう。
人気ランキングの活用
一時払い終身保険を選ぶ際、多くの人が参考にするのが、保険比較サイトや雑誌などで紹介されている「人気ランキング」です。
これらのランキングは、現在どのような商品が市場で注目を集めているのか、そのトレンドを知るための有効な手がかりとなります。
ランキングで上位に挙げられる一時払い終身保険には、いくつかの共通した傾向が見られることがあります。
例えば、大手生命保険会社の商品は、長年の実績とブランド力による安心感から、根強い人気を保っていることが多いようです。
また、近年ではインターネット専業の生命保険会社(ネット生保)の商品も、比較的シンプルな保障内容と手頃な保険料設定で支持を集めています。
商品の特性としては、やはり相続税対策としての活用を意識したものが多くランクインする傾向にあります。
具体的には、非課税枠を意識した保険金額設定がしやすい商品や、高齢でも加入しやすい商品などが注目されやすいでしょう。
加えて、貯蓄性を重視する観点から、返戻率の高さもランキングの順位を左右する重要な要素となります。
特に、円建てよりも高い利回りが期待できる「外貨建て一時払い終身保険」は、リスクを理解した上で資産運用の一環として活用したい層からの人気を集め、ランキング上位に顔を出すことも少なくありません。
ただし、ランキング情報を参考にする際には注意が必要です。
まず、どのような基準(例:申込件数、資料請求数、顧客満足度、返戻率など)に基づいて作成されたランキングなのかを確認することが大切です。
基準によって順位は大きく変動する可能性があります。
また、ランキング情報は常に最新のものとは限りません。
保険商品は頻繁に改定され、経済情勢(金利や為替レート)によっても商品の魅力度は変化するため、情報の鮮度を確認することが重要です。
ランキングはあくまで市場の動向を知るための一つの指標と捉え、最終的な商品選択は、ご自身の状況や目的に照らし合わせ、必要であれば専門家のアドバイスも参考にしながら、個別に判断することが最も賢明な方法と言えるでしょう。

一番人気なのは?商品の特徴
「終身保険で一番人気なのはどれか?」という問いに対して、一概に特定の商品名を挙げることは難しいと言えます。
なぜなら、保険加入者の年齢、家族構成、経済状況、そして保険に求める目的(保障重視か、貯蓄性重視か、相続対策かなど)によって、「最適な保険=一番人気」は異なるからです。
しかし、一般的に多くの人に選ばれやすい、あるいは人気が集まりやすい終身保険には、いくつかの共通した特徴が見られます。
まず、保障内容と保険料のバランスが良い商品が挙げられます。
十分な死亡保障を確保しつつ、保険料負担が過度にならない商品は、幅広い層から支持されやすい傾向にあります。
特に、インターネット経由で申し込みができるネット生保の商品は、人件費や店舗コストを抑えることで、比較的リーズナブルな保険料を実現している場合が多く、人気を集めています。
次に、貯蓄性の高さも重要な要素です。
将来の資産形成や、老後資金の準備なども視野に入れる場合、解約返戻率が高い商品は魅力的です。
ただし、返戻率を高めるために保険料が高めに設定されている場合もあるため、保障とのバランスを考慮する必要があります。
また、保険会社の信頼性や経営の安定性も、多くの人が重視するポイントです。
長期間にわたる契約となるため、万が一の際にも確実に保険金が支払われるという安心感は、商品選択において大きなウェイトを占めます。
加えて、加入のしやすさも人気の要因となり得ます。
健康状態に不安がある方でも加入しやすいように、告知項目を限定した「引受基準緩和型」の終身保険は、近年ニーズが高まっています。
保険料は割高になる傾向がありますが、持病などを理由にこれまで保険加入を諦めていた層にとっては、有力な選択肢となります。
支払い方法という点では、相続対策を主目的とする場合は「一時払い終身保険」が人気ですが、毎月の負担を抑えたい、あるいは生命保険料控除を毎年利用したいという場合は、「月払い」や「年払い」の終身保険が選ばれるでしょう。
最近のトレンドとしては、円建てだけでなく「外貨建て」の終身保険や、保険料払込期間中の解約返戻金を低く抑える代わりに保険料を割安にした「低解約返戻金型」の終身保険なども注目されています。
結局のところ、「一番人気」の定義は人それぞれです。
様々な商品の特徴を比較検討し、ご自身のライフプランや価値観に最も合致する終身保険を見つけることが重要となります。

一時払い 終身保険 の 相続税対策 比較 :総まとめ
次のように記事の内容をまとめました。
- 一時払い終身保険は相続対策に有効な選択肢の一つである
- 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が存在する
- 生命保険の非課税枠は相続税の基礎控除とは別枠で適用される
- 死亡保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象外となる
- 保険金受取人は比較的速やかに現金を受け取ることが可能である
- 保険金は納税資金や葬儀費用、代償分割の原資に活用できる
- 受取人を指定することで特定の人へ確実に財産をのこせる
- 現預金の相続財産評価額を圧縮する効果が期待できる
- 高齢者(80歳以上など)でも加入しやすい商品がある
- 加入時にはまとまった一括払いの資金が必要である
- 早期解約した場合、元本割れするリスクがある
- 生命保険料控除は保険料を支払った初年度のみ利用可能である
- 契約形態(契約者・被保険者・受取人)によって課税される税金の種類が異なる
- 返戻率は重要な指標だが、為替リスク(外貨建ての場合)なども考慮が必要である
- 保険選びはランキングだけでなく、個々の状況や目的に合わせて総合的に判断すべきである