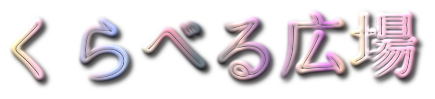身体の内部を詳しく調べるために、CT検査やMRI検査といった画像検査が用いられます。
これらの検査は、使用する機械や撮影方法が異なるため、料金や得意とする分野にも違いが見られます。
レントゲン検査と比較して、CT検査はより詳細な情報が得られ、MRI検査は放射線被曝がないというメリットがあります。
しかし、CT検査もMRI検査も、それぞれに長所と短所があり、目的とする検査によって適切な選択肢が変わってきます。
ここでは、CT検査とMRI検査の違いについて、画像の見え方や造影剤の種類、心臓や膵臓の検査における使い分けなど、様々な観点からわかりやすく解説していきます。
また、看護学生の方にも理解しやすいように、各検査の原理や看護のポイントについても詳しく説明します。
さらに、MRIとCTの両方を受ける必要性や、整形外科領域でのそれぞれの活用法についてもご紹介します。
この記事を読むことで、CT検査とMRI検査の違いを深く理解し、検査を受ける際の不安を解消できるでしょう。

- CTとMRIの基本的な原理と、画像化される情報
- 料金や検査時間など、検査を受ける上で重要な要素
- CT、MRI、レントゲンの各検査の得意分野と使い分け
- 病気の種類に応じた、最適な検査の選び方
本記事の内容
CTとMRIの違いとは?検査の基本を解説
- 料金と費用
- 看護学生向け解説
- 仕組みと得意分野をわかりやすく解説
- CTとレントゲンの違いについて
- 撮影と撮像の違い:医療用語
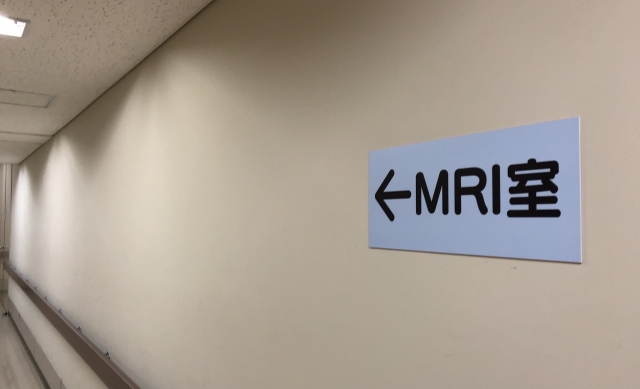
料金と費用
CT検査とMRI検査では、使用する機械や撮影方法が異なるため、料金にも差が見られます。
どちらの検査を選ぶべきかは、検査部位や目的によって変わってきます。
一般的に、CT検査はMRI検査よりも比較的安価な傾向があります。
料金は医療機関によって異なりますが、おおよその目安として、CT検査は1部位あたり数千円から1万円程度、MRI検査は1部位あたり1万円から3万円程度が相場です。
ただし、造影剤を使用するかどうか、撮影範囲、医療機関の種類(大学病院、一般病院、クリニックなど)によっても料金は変動します。
また、人間ドックや健康診断でCTやMRIをオプションとして追加する場合、料金は別途設定されていることが多いです。
例えば、頭部MRIドックは2万円程度、プレミアム乳がんドックは5万円程度といった料金設定が見られます。
どちらの検査を受けるべきか迷う場合は、医師に相談し、検査の目的や費用などを考慮して判断することが大切です。
| 検査の種類 | 料金の目安 (1部位) | 特徴 |
|---|---|---|
| CT検査 | 数千円~1万円程度 | 比較的安価 短時間で広範囲の撮影が可能 |
| MRI検査 | 1万円~3万円程度 | 放射線被曝がない 軟部組織の描出に優れている |
| 頭部MRIドック | 2万円程度 | 脳卒中リスクの評価に有用 |
| 乳がんドック | 5万円程度 | 乳がんの早期発見に有用 |
看護学生向け解説
CT検査とMRI検査は、どちらも医療現場でよく用いられる画像検査ですが、その原理や得意とする分野には大きな違いがあります。
看護学生の皆さんにとって、これらの違いを理解することは、患者さんのケアや検査の説明において非常に重要です。
CT(Computed Tomography:コンピュータ断層撮影)検査は、X線を利用して体の断面像を撮影する検査です。
X線を360度から照射し、その吸収率の違いをコンピュータで解析することで、骨や臓器の形状を詳細に描出します。
CT検査のメリットは、検査時間が短く、骨の描出に優れていることです。
一方、デメリットとしては、放射線被曝があること、軟部組織のコントラストが低いことが挙げられます。
MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像)検査は、強い磁場と電波を利用して体の断面像を撮影する検査です。
体内の水素原子に磁場をかけ、電波を照射することで、各組織からの信号を検出します。
MRI検査のメリットは、放射線被曝がないこと、軟部組織のコントラストに優れていることです。
デメリットとしては、検査時間が長く、金属製のものが体内にある場合は検査ができないこと、大きな音がすることなどが挙げられます。
看護学生の皆さんは、CT検査とMRI検査の違いを理解し、それぞれの検査の目的や注意点を把握することで、患者さんに適切な情報提供やサポートができるようになるでしょう。
| 項目 | CT検査 | MRI検査 |
|---|---|---|
| 原理 | X線 | 磁場と電波 |
| メリット | 短時間 骨の描出に優れる | 放射線被曝なし 軟部組織のコントラストが良い |
| デメリット | 放射線被曝 軟部組織のコントラストが低い | 検査時間が長い 金属に注意 騒音 |
| 得意な分野 | 骨折 肺の病変 出血 | 脳、脊髄、関節、 軟部組織 |
| 看護のポイント | 放射線防護 検査前の金属チェック 体位変換の介助 | 検査前の金属チェック 閉所恐怖症への配慮 騒音対策 体位変換の介助 |
仕組みと得意分野をわかりやすく解説
CTとMRIは、どちらも身体の内部を画像化する検査ですが、その仕組みと得意分野が異なります。
CTは、X線を使って身体の断面を撮影する検査です。
一方、MRIは、磁石と電波を使って身体の断面を撮影する検査です。
CTのメリットは、検査時間が短く、骨や肺の描出に優れていることです。
デメリットは、放射線被曝があること、軟部組織のコントラストが低いことです。
MRIのメリットは、放射線被曝がないこと、軟部組織のコントラストに優れていることです。
デメリットは、検査時間が長く、金属製のものが体内にある場合は検査ができないこと、大きな音がすることです。
CTは、骨折や肺の病変、出血などの診断に適しています。
一方、MRIは、脳や脊髄、関節、軟部組織などの診断に適しています。
どちらの検査を受けるべきかは、検査の目的や症状によって異なります。
医師に相談し、適切な検査を選択することが大切です。
| 項目 | CT検査 | MRI検査 |
|---|---|---|
| 原理 | X線 | 磁石と電波 |
| メリット | 短時間 骨や肺の描出に優れる | 放射線被曝なし 軟部組織のコントラストが良い |
| デメリット | 放射線被曝 軟部組織のコントラストが低い | 検査時間が長い 金属に注意、騒音 |
| 得意な分野 | 骨折、肺の病変、出血 | 脳、脊髄、関節、 軟部組織 |
CTとレントゲンの違いについて
CT検査とレントゲン検査は、どちらもX線を利用した画像検査ですが、得られる情報量や適応となる病気が異なります。
レントゲン検査は、X線を身体に照射し、その透過具合をフィルムに記録することで、骨や臓器の画像を一枚の平面画像として表示します。
レントゲン検査のメリットは、検査時間が非常に短く、被曝量が少ないこと、そして安価であることです。
一方、デメリットは、得られる情報が少ないこと、骨や空気のコントラストが強いため、軟部組織の描出が難しいことです。
CT検査は、X線を360度から照射し、その透過データをコンピュータで解析することで、身体の断面像を画像化します。
CT検査のメリットは、レントゲン検査よりも詳細な情報が得られること、骨や臓器の立体的な構造を把握できることです。
デメリットは、レントゲン検査よりも被曝量が多いこと、検査時間が長いこと、そして費用が高いことです。
レントゲン検査は、骨折や肺炎などのスクリーニング検査に適しています。
一方、CT検査は、レントゲン検査では診断が難しい病気や、より詳細な情報を必要とする場合に適しています。
| 項目 | レントゲン検査 | CT検査 |
|---|---|---|
| 原理 | X線 | X線を360度から照射 |
| メリット | 短時間、低被曝、安価 | 詳細な情報 立体的な構造把握 |
| デメリット | 情報量が少ない 軟部組織の描出が難しい | 被曝量が多い 検査時間が長 高価 |
| 適応となる病気 | 骨折 肺炎などの スクリーニング検査 | レントゲン検査で診断が難しい病気 詳細な情報が必要な場合 |
撮影と撮像の違い:医療用語
医療現場では、「撮影」と「撮像」という言葉が、画像検査に関連して使われますが、両者にはニュアンスの違いがあります。
一般的に、「撮影」は、レントゲン検査のように、X線や光などのエネルギーを直接フィルムやイメージセンサーに当てて画像を記録する場合に使われます。
一方、「撮像」は、CT検査やMRI検査のように、コンピュータを使って画像を再構成する場合に使われることが多いです。
しかし、実際には、「撮影」と「撮像」は厳密に区別されておらず、どちらの言葉を使っても意味が通じることがほとんどです。
例えば、「レントゲン撮影」や「CT撮影」という言葉もよく使われますし、「MRI撮像」や「エコー撮像」という言葉も使われます。
医療従事者の中には、画像の取得方法によって「撮影」と「撮像」を使い分ける人もいますが、一般の人がこれらの言葉を区別する必要はあまりありません。
ただし、医療関係者とコミュニケーションを取る際には、相手がどのような意図でこれらの言葉を使っているのかを理解することが大切です。
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 撮影 | X線や光などのエネルギーを直接フィルムや イメージセンサーに当てて画像を記録する場合 | レントゲン撮影 内視鏡撮影 |
| 撮像 | コンピュータを使って画像を 再構成する場合 | CT撮像 MRI撮像 エコー撮像 |
MRICTの違いを徹底比較!病気別選び方
- 画像で見る
- 造影剤を使う検査の違い
- 心臓MRIとCTの違いは何ですか?
- 膵臓の検査にはどっちを選ぶ?
- どちらが正確ですか?
- 両方受ける必要性は?

画像で見る
CTとMRIは、どちらも身体の内部を画像化する検査ですが、その原理が異なるため、画像の見え方にも違いがあります。
CT画像は、X線を使って身体の断面を撮影するため、骨や空気のコントラストが強く、白黒の画像として表示されます。
骨は白く、空気は黒く描出されるのが特徴です。
一方、MRI画像は、磁石と電波を使って身体の断面を撮影するため、軟部組織のコントラストが高く、様々な色調の画像として表示されます。
筋肉や脂肪、臓器などが、それぞれ異なる色で描出されるのが特徴です。
CT画像は、骨折や肺の病変、出血などの診断に適しています。
MRI画像は、脳や脊髄、関節、軟部組織などの診断に適しています。
例えば、脳のCT画像では、出血や骨折の有無を判断することができます。
一方、脳のMRI画像では、脳梗塞や脳腫瘍などの早期発見に役立ちます。
このように、CTとMRIの画像は、それぞれ異なる情報を提供してくれるため、医師は検査の目的や症状に応じて、適切な検査を選択します。
| 項目 | CT画像 | MRI画像 |
|---|---|---|
| 原理 | X線 | 磁石と電波 |
| コントラスト | 骨や空気のコントラストが強い | 軟部組織のコントラストが高い |
| 画像の色調 | 白黒 | 多様な色調 |
| 得意な分野 | 骨折、肺の病変、出血 | 脳、脊髄、関節、軟部組織 |
| 画像例 | 骨が白く、 空気が黒く描出される | 筋肉や脂肪、臓器などが、 それぞれ異なる色で描出される |
造影剤を使う検査の違い
CT検査とMRI検査では、必要に応じて造影剤を使用することがあります。
造影剤とは、血管や臓器をより鮮明に描出するために使用する薬剤のことです。
CT検査で使用する造影剤は、主にヨード造影剤です。
ヨード造影剤は、X線の吸収率を高める効果があり、血管や臓器を白く描出します。
一方、MRI検査で使用する造影剤は、主にガドリニウム造影剤です。
ガドリニウム造影剤は、磁場の影響を受けやすく、血管や臓器の信号強度を変化させる効果があります。
CT造影剤とMRI造影剤は、それぞれ副作用のリスクが異なります。
CT造影剤では、アレルギー反応や腎機能障害が起こることがあります。
MRI造影剤では、腎性全身性線維症(NSF)という重篤な副作用がまれに起こることがあります。
そのため、造影剤を使用する際には、医師は患者さんの既往歴やアレルギー歴などを確認し、慎重に判断します。
| 項目 | CT造影剤 | MRI造影剤 |
|---|---|---|
| 主な種類 | ヨード造影剤 | ガドリニウム造影剤 |
| 効果 | X線の吸収率を高める | 磁場の影響を受けやすく、 信号強度を変化させる |
| 副作用のリスク | アレルギー反応 機能障害 | 腎性全身性線維症(NSF) |
| 注意点 | 既往歴やアレルギー歴の確認 | 腎機能障害のある患者さんには慎重投与 |
心臓MRIとCTの違いは何ですか?
心臓の検査には、心臓MRIと心臓CTという2つの代表的な画像検査があります。
どちらの検査も、心臓の形態や機能を評価することができますが、それぞれに特徴と得意分野があります。
心臓MRIは、磁石と電波を使って心臓の断面像を撮影する検査です。
心臓MRIのメリットは、放射線被曝がないこと、心臓の筋肉や血管、弁などの軟部組織のコントラストに優れていることです。
また、心臓MRIは、心臓の動きや血流を評価することもできます。
一方、心臓CTは、X線を使って心臓の断面像を撮影する検査です。
心臓CTのメリットは、検査時間が短く、心臓の血管(冠動脈)を詳細に描出できることです。
特に、石灰化の評価に優れています。
心臓MRIは、心筋梗塞や心筋症、弁膜症などの診断に適しています。
心臓CTは、狭心症や冠動脈疾患の診断に適しています。
どちらの検査を受けるべきかは、検査の目的や症状によって異なります。
医師に相談し、適切な検査を選択することが大切です。
| 項目 | 心臓MRI | 心臓CT |
|---|---|---|
| 原理 | 磁石と電波 | X線 |
| メリット | 放射線被曝がない 軟部組織のコントラストが良い 心臓の動きや血流を評価できる | 検査時間が短い 冠動脈の描出に優れる 石灰化の評価に優れる |
| デメリット | 検査時間が長い 金属製のものが体内にある場合は 検査ができない | 放射線被曝がある 軟部組織のコントラストが低い |
| 適応となる病気 | 心筋梗塞 心筋症 弁膜症 | 狭心症 冠動脈疾患 |
膵臓の検査にはどっちを選ぶ?
膵臓の検査には、CT検査とMRI検査という2つの代表的な画像検査があります。
どちらの検査も、膵臓の形態や病変の有無を評価することができますが、それぞれに特徴と得意分野があります。
CT検査は、X線を使って膵臓の断面像を撮影する検査です。
CT検査のメリットは、検査時間が短く、膵臓全体のスクリーニングに適していることです。
特に、膵臓がんの発見や、膵臓周囲の血管との関係を評価するのに役立ちます。
一方、MRI検査は、磁石と電波を使って膵臓の断面像を撮影する検査です。
MRI検査のメリットは、放射線被曝がないこと、膵臓の内部構造や病変の性状を詳細に評価できることです。
特に、膵管の描出に優れており、膵管内腫瘍の診断に役立ちます。
膵臓がんの疑いがある場合や、膵臓の詳しい検査が必要な場合には、MRI検査が推奨されることが多いです。
ただし、CT検査もMRI検査も、それぞれに得意分野があるため、医師は患者さんの症状や検査の目的に応じて、適切な検査を選択します。
| 項目 | CT検査 | MRI検査 |
|---|---|---|
| 原理 | X線 | 磁石と電波 |
| メリット | 検査時間が短い 膵臓全体のスクリーニングに 適している | 放射線被曝がない 膵臓の内部構造や病変の性状を 詳細に評価できる 膵管の描出に優れる |
| デメリット | 放射線被曝がある 膵臓の内部構造や 病変の性状の評価には限界がある | 検査時間が長い 金属製のものが体内にある場合は 検査ができない |
| 適応となる病気 | 膵臓がんのスクリーニング 膵臓周囲の血管との関係の評価 | 膵臓がんの疑いがある場合 膵臓の詳しい検査が必要な場合 膵管内腫瘍の診断 |
どちらが正確ですか?
MRIとCTは、どちらも高度な画像検査であり、それぞれ得意とする分野が異なるため、どちらが「正確」であるかを一概に言うことはできません。
CT検査は、X線を使って身体の断面を撮影するため、骨や空気のコントラストが強く、骨折や肺の病変、出血などの診断に適しています。
また、検査時間が短いため、緊急性の高い病気の診断にも役立ちます。
MRI検査は、磁石と電波を使って身体の断面を撮影するため、軟部組織のコントラストが高く、脳や脊髄、関節、筋肉、靭帯などの診断に適しています。
また、放射線被曝がないというメリットもあります。
例えば、骨折の診断においては、CT検査の方がMRI検査よりも優れていると言えます。
一方、脳腫瘍の診断においては、MRI検査の方がCT検査よりも優れていると言えます。
このように、MRIとCTは、それぞれ異なる情報を提供してくれるため、医師は検査の目的や症状に応じて、適切な検査を選択します。
どちらの検査を受けるべきか迷う場合は、医師に相談し、検査の目的やメリット・デメリットなどを考慮して判断することが大切です。
| 項目 | CT検査 | MRI検査 |
|---|---|---|
| 原理 | X線 | 磁石と電波 |
| 得意な分野 | 骨折、肺の病変、出血など | 脳、脊髄、関節、筋肉、靭帯など |
| メリット | 検査時間が短い 緊急性の高い病気の診断に役立つ | 放射線被曝がない 軟部組織のコントラストが高い |
| どちらが正確か | 病気の種類や検査の目的によって異なる | 病気の種類や検査の目的によって異なる |
両方受ける必要性は?
MRI検査とCT検査は、それぞれ異なる原理に基づいており、得意とする分野も異なるため、病状によっては両方の検査を受ける必要が出てくる場合があります。
例えば、脳卒中の疑いがある場合、CT検査で出血の有無を迅速に確認し、MRI検査でより詳細な脳の状態を評価することがあります。
CT検査は、出血の診断に優れており、MRI検査は、脳梗塞の早期発見や、脳の微細な病変の評価に優れています。
また、がんの診断においても、CT検査でがんの広がりや転移の有無を確認し、MRI検査でがんの性状や周囲の組織との関係を評価することがあります。
CT検査は、肺がんや肝臓がんなどの診断に適しており、MRI検査は、乳がんや前立腺がんなどの診断に適しています。
このように、MRI検査とCT検査は、互いに補完し合うことで、より正確な診断を可能にします。
医師は、患者さんの症状や検査の目的に応じて、MRI検査とCT検査を適切に組み合わせ、最適な医療を提供します。
| 検査の組み合わせ例 | 目的 |
|---|---|
| CT検査 + MRI検査 | 脳卒中の診断、がんの診断、 原因不明の症状の精査など |
| CT検査 (スクリーニング) + MRI検査 (精密検査) | スクリーニング検査で異常が見つかった場合に、 より詳しい検査を行う |
MRICTの違い:この記事のまとめ
次のように記事の内容をまとめました。
- CT検査はX線、MRI検査は磁場と電波を利用する
- CT検査は短時間、MRI検査は長時間を要する
- CT検査は骨や肺の描出に優れ、MRI検査は軟部組織の描出に優れる
- CT検査には放射線被曝のリスクがあるが、MRI検査にはない
- CT検査は骨折や肺の病変の診断に、MRI検査は脳や脊髄、関節の診断に適している
- CT検査は比較的安価で、MRI検査は高価な傾向がある
- CT検査造影剤はヨード造影剤、MRI検査造影剤はガドリニウム造影剤を使用する
- 心臓MRIは心臓の筋肉や弁の評価に優れ、心臓CTは冠動脈の評価に優れる
- 膵臓CT検査は膵臓全体のスクリーニングに、膵臓MRI検査は膵管の評価に適する
- MRIとCTはそれぞれ得意分野が異なるため、両方の検査が必要になる場合もある
- 「撮影」はX線を直接フィルムに当てる場合に、「撮像」はコンピュータで再構成する場合に使うことが多い
- MRI検査を受ける際には、金属製のものを身につけてはいけない
- CT検査は、レントゲン検査よりも詳細な情報が得られる
- 看護学生は、CT検査とMRI検査の違いを理解し、患者への適切な情報提供に努める必要がある
- 検査を選ぶ際は、医師と相談し、検査の目的や費用を考慮することが重要だ