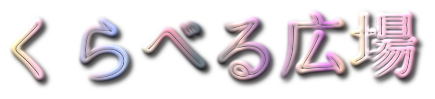最近、金色と銀色の新しい500円玉を見かけることが増えましたが、以前の500円玉と具体的にどう違うのか、見分け方はあるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
そもそも500円玉はいつから変わったのか、歴代のデザインにはどのような変遷があったのか、その種類や五百円硬貨の構成、つまり素材の違いについても知りたいですよね。
また、新しい500円玉と古いものでは重さが違うのか、側面のギザギザの違いは何ですか、といった細かな点も疑問に思うかもしれません。
実用的な面では、新500円玉が一部の自動販売機で使えないという話もありますし、逆に旧500円玉は今でもコンビニで問題なく使えるのかも気になるところです。
さらに、切り替え時期にあたる令和3年発行の旧500円玉はレアなのか、という関心を持つ方もいるでしょう。
この記事では、そうした500円硬貨の新旧に関する様々な疑問点、見分け方から素材、使える場所まで、詳しく解説していきます。

記事のポイントです。
- 見た目や触感で新旧500円玉を簡単に見分ける方法
- 素材・重さ・偽造防止技術など性能面での具体的な違い
- いつからどのデザインに変わったかの歴史と発行時期
- 新旧硬貨それぞれの現在の利用可否や注意点
本記事の内容
500円玉 の 新旧 の 違い 、見分け方を解説
- 簡単な見分け方は?
- デザイン変更はいつからですか?
- 重さは世代で違いますか?
- 側面デザインの明確な違い
- 硬貨の構成(素材)の違い
- 裏の花のデザインは同じ?
簡単な見分け方は?
旧500円玉と新500円玉は、いくつかの明確な違いによって簡単に見分けることができます。
最もわかりやすいのは、硬貨全体の見た目の色でしょう。
旧500円玉(2代目・平成12年発行)は全体が銀色に近い単一の色(ニッケル黄銅)であるのに対し、新500円玉(3代目・令和3年発行)は中央部が銀色、外周部が金色という2色の構造(バイカラー)になっています。

この色の違いは「バイカラー技術」によるもので、一目で新旧を判別できる大きな特徴です。
また、手で触れた際の側面の感触も異なります。
旧500円玉は均一な斜めのギザギザですが、新500円玉は「異形斜めギザ」と呼ばれる、部分的に形状が異なるギザギザが採用されました。
これは触感でも識別しやすくするための工夫であり、世界初の技術とされています。
さらに、細かな点ですが、新500円玉には「JAPAN」や「500YEN」といった微細文字が縁に追加されています。
旧500円玉にもあった潜像(傾けると文字が見える技術)も、新500円玉ではデザインが変更され、より高度なものになりました。
これらの点を比較することで、誰でも容易に新旧の500円玉を見分けることが可能です。
| 比較項目 | 旧500円玉(2代目) | 新500円玉(3代目) |
|---|---|---|
| 色 | 単色(銀色系) | 2色(中央:銀色、外周:金色) |
| 側面ギザ | 斜めギザ | 異形斜めギザ |
| 微細文字 | なし | あり(JAPAN, 500YEN) |
| 潜像(00部分) | 500円 | JAPAN / 500YEN |
デザイン変更はいつからですか?
500円玉のデザイン変更は、主に偽造防止技術の向上を目的として行われてきました。
現在までに大きく分けて3つの世代が存在し、それぞれの発行開始時期は以下の通りです。
初代500円玉は、昭和57年(1982年)4月1日に発行が開始されました。
これは、それまで流通していた500円紙幣(岩倉具視の肖像)に代わるものとして登場した最初の500円硬貨です。
素材は白銅で、側面には「NIPPON ◆」という文字が繰り返し刻印されていました。
次に、2代目500円玉が登場したのは平成12年(2000年)です。
初代の偽造問題に対応するため、素材をニッケル黄銅に変更し、電気的な特性を変えました。
また、側面は文字から均一な「斜めギザ」に変更され、視覚障がいのある方にも配慮したデザインとなりました。
そして、現在流通している最新の3代目500円玉は、令和3年(2021年)11月1日から発行が開始されました。
本格的な流通は少し遅れて進みましたが、バイカラー・クラッド技術や異形斜めギザといった、さらに高度な偽造防止技術が導入されています。
このように、500円玉のデザインは、昭和、平成、令和という時代の節目に合わせて進化してきたと言えるでしょう。
| 世代 | 発行開始年 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 初代 | 昭和57年 (1982年) | 白銅製、側面は文字(NIPPON ◆) |
| 2代目 | 平成12年 (2000年) | ニッケル黄銅製、側面は斜めギザ、潜像技術導入 |
| 3代目 | 令和3年 (2021年) | バイカラー・クラッド、異形斜めギザ、微細文字など最新技術導入 |
重さは世代で違いますか?
はい、500円玉の重さは世代によってわずかに異なります。
これは、使用されている素材の構成や密度が変わったことによるものです。
初代500円玉(昭和57年発行)の重さは約7.2グラムでした。
素材は白銅(銅75%、ニッケル25%)です。
2代目500円玉(平成12年発行)は、偽造防止のために素材がニッケル黄銅(銅72%、亜鉛20%、ニッケル8%)に変更されたことに伴い、重さが約7.0グラムと、わずかに軽くなりました。
そして、最新の3代目500円玉(令和3年発行)は、バイカラー・クラッド技術の採用により、3種類の金属(ニッケル黄銅、白銅、銅)が組み合わされています。
その結果、重さは約7.1グラムとなり、2代目より0.1グラム重くなりました。
ただし、これらの重さの違いは非常にわずかであり、手で持っただけではほとんど区別がつきません。
精密な計量器で測らない限り、その差を感じることは難しいでしょう。
重さの違いは、主に自動販売機などの硬貨選別機が偽造硬貨を判別するための一つの要素として重要になります。
| 世代 | 発行開始年 | 重さ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 昭和57年 (1982年) | 約 7.2g | 白銅 |
| 2代目 | 平成12年 (2000年) | 約 7.0g | ニッケル黄銅 |
| 3代目 | 令和3年 (2021年) | 約 7.1g | バイカラー・クラッド(3種の金属) |
なお、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令」により、貨幣の量目(重さ)には許容誤差(公差)が定められています。
側面デザインの明確な違い
500円玉の側面(縁)のデザインは、新旧で明確な違いがあります。
これは偽造防止効果を高めるとともに、触感による識別をしやすくするための重要な変更点です。
初代500円玉(昭和57年発行)の側面には、ギザギザではなく「NIPPON ◆」という文字が等間隔で刻印されていました。
これは当時の硬貨としては特徴的なものでした。
2代目500円玉(平成12年発行)では、偽造防止の強化とデザインの変更が行われ、側面は均一な「斜めギザ」になりました。
これは他の額面の硬貨(例:100円玉)のギザギザとは異なり、斜めに入っているのが特徴です。
そして、最新の3代目500円玉(令和3年発行)では、世界で初めて「異形斜めギザ」が採用されました。
これは、基本的な斜めギザの中に、上下左右の4箇所だけ、他の部分とは異なる形状(幅が広いなど)のギザが配置されているものです。
この不規則なギザギザは、従来のギザよりも偽造が格段に難しくなっており、指で触れただけでも旧型との違いを感じ取ることができます。

このように、側面のデザインは単なる装飾ではなく、各時代の最新技術を反映した偽造防止策の進化を示しているのです。
| 世代 | 発行開始年 | 側面のデザイン | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 昭和57年 (1982年) | 文字(NIPPON ◆) | ギザギザではない |
| 2代目 | 平成12年 (2000年) | 斜めギザ | 均一な斜めのギザ |
| 3代目 | 令和3年 (2021年) | 異形斜めギザ | 世界初、部分的に形状が異なるギザが 不規則に配置されている |
硬貨の構成(素材)の違い
五百円硬貨の構成、つまり使われている素材は、世代ごとに大きく異なります。
素材の変更は、偽造防止性能の向上、耐久性の強化、そして製造コストの最適化といった複数の目的から行われてきました。
初代500円玉(昭和57年発行)は、「白銅(はくどう)」と呼ばれる合金で作られていました。
これは銅75%、ニッケル25%の配合で、当時の100円硬貨と同じ素材でした。
しかし、この素材は偽造されやすかったという問題点がありました。
そこで、2代目500円玉(平成12年発行)では、素材が「ニッケル黄銅」に変更されました。
配合は銅72%、亜鉛20%、ニッケル8%です。
この変更により、電気伝導率などの物理的特性が変わり、自動販売機などで偽造硬貨を判別しやすくなりました。
そして、最新の3代目500円玉(令和3年発行)では、さらに複雑な構造が採用されています。
中心部分と外周部分で異なる金属を使用する「バイカラー技術」と、異なる種類の金属板をサンドイッチ状に重ね合わせる「クラッド技術」を組み合わせた「バイカラー・クラッド」構造となっています。
具体的には、中心の円盤部分は、銅を白銅で挟んだ3層構造(クラッド)になっており、その周りをニッケル黄銅製のリングが囲んでいます。
これにより、見た目が2色になるだけでなく、電気的特性がより複雑になり、偽造が極めて困難になりました。
また、表面を硬い金属で覆うことで耐久性も向上しています。
| 世代 | 発行開始年 | 素材・構造 | 主な構成金属 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 昭和57年 (1982年) | 白銅(単一素材) | 銅、ニッケル |
| 2代目 | 平成12年 (2000年) | ニッケル黄銅(単一素材) | 銅、亜鉛、ニッケル |
| 3代目 | 令和3年 (2021年) | バイカラー・クラッド (3層構造クラッド材 + リング) | ニッケル黄銅、白銅、銅 |
このように、素材構成の進化は、500円硬貨の信頼性と安全性を高める上で非常に重要な役割を果たしているのです。
裏の花のデザインは同じ?
結論から言うと、500円玉の裏面に描かれている「竹」と「橘(たちばな)」のデザインは、初代から最新の3代目まで基本的に同じものが採用されています。
表面のデザインである「桐(きり)」も同様に、基本的な図柄は変更されていません。

これらのデザインは、日本の文化や伝統において縁起が良いとされる植物が選ばれています。
竹は成長の速さやまっすぐに伸びる姿から生命力や繁栄を象徴し、橘は古事記にも登場する常緑樹で、長寿や子孫繁栄の象徴とされています。
表面の桐も、古くから高貴な紋章として用いられ、日本政府の紋章(五七の桐)としても知られています。
ただし、デザインの基本的なモチーフは同じですが、偽造防止技術の進化に伴い、細部の表現や加工は変更されています。
例えば、2代目以降の500円玉では、表面の「日本国」や「五百円」の文字の周囲、裏面の模様の一部などに、髪の毛よりも細い「微細線」と呼ばれる線模様が加えられました。
これは、コピーによる偽造を防ぐための高度な技術です。
また、3代目の新500円玉では、これらの微細加工がさらに精緻になっている可能性があります。
したがって、「裏の花(植物)」の基本的なデザイン自体は変わっていませんが、硬貨全体のデザインとしては、偽造防止技術の組み込みによって細かな違いが存在すると言えます。
知っておきたい! 500円玉 の 新旧 の 違い と流通
- いつから変わった?発行時期は?
- 歴代デザインの変遷
- 種類と偽造防止技術
- 新500円は使えない場所はある?
- 旧500円はコンビニで使えますか?
- 令和3年の旧500円玉はレア?
いつから変わった?発行時期は?
500円玉は、その誕生から現在までに2回の大きなモデルチェンジを経ており、発行時期によってデザインや素材が異なります。

まず、最初の500円玉(初代)が発行されたのは、昭和57年(1982年)4月1日です。
これは、当時流通していた500円紙幣(岩倉具視の肖像)の代替として登場しました。
自動販売機の普及や、紙幣よりも耐久性が高いという利点から硬貨への移行が進められました。
次に、現在でも広く流通している2代目の500円玉は、平成12年(2000年)に発行が開始されました。
初代500円玉の偽造が多発したことを受けて、素材を白銅からニッケル黄銅に変更し、電気抵抗値を変えるなどの偽造防止対策が施されたのが主な理由です。
側面も文字から斜めギザに変更されました。
そして、最新の3代目500円玉は、令和3年(2021年)11月1日から発行が開始されました。
さらなる偽造防止技術の強化を目的として、「バイカラー・クラッド」技術や「異形斜めギザ」といった、より高度な技術が導入されています。
このように、500円玉が変わったタイミングは主に偽造問題への対策であり、約20年の周期で大きな変更が行われてきたことがわかります。
| 世代 | 発行開始年月 | 主な変更理由 |
|---|---|---|
| 初代 | 昭和57年 (1982年) 4月 | 500円紙幣からの移行、耐久性向上 |
| 2代目 | 平成12年 (2000年) | 初代の偽造対策、素材変更 |
| 3代目 | 令和3年 (2021年) 11月 | さらなる偽造防止技術の強化 |
歴代デザインの変遷
500円玉のデザインは、発行された年代ごとに特徴的な変化を遂げてきました。
基本的な図柄(表面:桐、裏面:竹・橘)は継承されていますが、素材感、側面、そして細部の偽造防止技術において進化が見られます。
初代(昭和57年発行)は、白銅製で全体的に銀白色をしていました。
側面には「NIPPON ◆」という文字が刻印されており、ギザギザはありませんでした。
当時の硬貨としては独特のデザインです。
2代目(平成12年発行)になると、素材がニッケル黄銅に変更され、色味が初代よりもやや黄色みを帯びた銀色になりました。
最大の変化は側面で、文字から均一な「斜めギザ」に変更されました。
また、この世代から角度によって文字が見え隠れする「潜像」技術が導入されています。
3代目(令和3年発行)は、最も大きなデザイン変更が行われました。
「バイカラー・クラッド」技術により、中央部が銀色、外周部が金色という2色構造になり、見た目が大きく変わりました。
素材も3種類(ニッケル黄銅、白銅、銅)の組み合わせです。
側面には世界初の「異形斜めギザ」が採用され、触っただけでも違いがわかります。
さらに、縁には「JAPAN」「500YEN」といった微細文字が追加され、潜像のデザインも変更されるなど、偽造防止技術が大幅に強化されています。
このように、歴代のデザイン変遷は、時代の要請に応じた偽造防止技術の進化と密接に関わっています。
| 世代 | 発行年 | 色調 | 側面デザイン | 主な偽造防止技術 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 昭和57年 | 銀白色 | 文字 (NIPPON ◆) | (当時は基本的なもの) |
| 2代目 | 平成12年 | 黄色味の銀色 | 斜めギザ | 潜像、微細線、(素材変更) |
| 3代目 | 令和3年 | 2色 (金/銀) | 異形斜めギザ | バイカラー・クラッド、微細文字 |
種類と偽造防止技術
現在までに発行された500円玉は、大きく分けて3種類が存在し、それぞれ異なる偽造防止技術が施されています。
技術の進化に伴い、より高度で複雑な対策が講じられてきました。
- 初代500円玉(白銅貨・昭和57年発行):
当時は高額硬貨であり、基本的なデザイン自体がある程度の偽造抑止力を持っていましたが、現代の基準から見ると高度な偽造防止技術は限定的でした。
側面は文字刻印(NIPPON ◆)でした。 - 2代目500円玉(ニッケル黄銅貨・平成12年発行):
初代の偽造問題を受けて、多くの偽造防止技術が導入されました。
- 素材変更: 電気抵抗値の異なるニッケル黄銅を採用。
- 斜めギザ: 側面を均一な斜めギザに変更。
- 潜像: 見る角度によって「500円」の文字が浮かび上がる。
- 微細線: 文字や模様の周囲に髪の毛より細い線を多数刻む。
- 微細点: 模様(桐の中央部)に微細な穴加工を施す。
- 素材変更: 電気抵抗値の異なるニッケル黄銅を採用。
- 3代目500円玉(バイカラー・クラッド貨・令和3年発行):
2代目の技術を引き継ぎつつ、さらに最新技術が追加され、世界最高水準の偽造防止機能を持つとされています。
- バイカラー・クラッド:
2種類の金属(異なる色)を組み合わせた構造。中心部は3層構造。 - 異形斜めギザ:
側面のギザの一部形状を変え、不規則にする世界初の技術。 - 微細文字:
縁に「JAPAN」「500YEN」の微小な文字を刻印。 - 潜像の高度化:
潜像のデザインが変更され、「JAPAN」と「500YEN」の2種類が見えるように。
- バイカラー・クラッド:
これらの技術は、単独でも偽造を困難にしますが、複数組み合わせることでより強固な偽造防止効果を発揮します。
特に最新の3代目500円玉は、視覚、触覚、そして機械による判別のいずれにおいても偽造が極めて難しいように設計されています。

新500円は使えない場所はある?
はい、令和3年(2021年)11月に発行が開始された新500円玉(3代目)は、発行当初、一部の機械で利用できないという問題が発生しました。
現在も完全に対応が進んでいない可能性はあります。
その主な理由は、新旧硬貨で重さや素材、電気的特性が微妙に異なるため、自動販売機や券売機、両替機、コインパーキングの精算機、ゲームセンターの機器などに内蔵されている硬貨選別機(コインセレクター)が、新500円玉を正しく認識できなかったからです。
これらの機器は、投入された硬貨のサイズ、重さ、材質(電気伝導率など)を瞬時に測定し、本物かどうか、どの額面の硬貨かを判別しています。
新500円玉は、従来の500円玉とは異なる特性を持つため、既存の機器では「異物」や「偽造硬貨」として認識され、受け付けられなかったり、返却されたりするケースが多く見られました。
この問題に対応するためには、機器の硬貨選別機を新500円玉対応のものに交換したり、ソフトウェアをアップデートしたりする必要があります。
鉄道会社の券売機や大手飲料メーカーの自動販売機などでは比較的早く対応が進みましたが、中小企業が管理する自動販売機や旧型の機器、バスの運賃箱などでは、改修コストや手間がかかるため、対応が遅れたり、未対応のままになっているケースも存在します。
特に、2024年の新紙幣発行も控えていたため、機器の改修を新紙幣対応と同時に行うことを計画していた事業者も多く、新500円玉への対応が後回しになった側面もあります。
もし新500円玉が使えない場面に遭遇した場合は、旧500円玉や他の硬貨、あるいは他の支払い方法(キャッシュレス決済など)を利用する必要があります。

旧500円はコンビニで使えますか?
はい、旧500円玉(主に平成12年発行の2代目ニッケル黄銅貨)は、現在も日本の正式な法定通貨であり、コンビニエンスストアを含むほとんどのお店で問題なく使用できます。
新500円玉(3代目バイカラー・クラッド貨)が発行された後も、旧500円玉が使えなくなるわけではありません。
日本の法律(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律)では、一度発行された貨幣は、特別な法令による廃止措置が取られない限り、無期限で通用すると定められています。
したがって、コンビニのレジでの支払いや、セルフレジ(通常、新旧両対応している場合が多い)などで、旧500円玉を他の硬貨と同じように使うことができます。
店員さんが受け取りを拒否することは、原則としてありません。
新旧の硬貨は当面の間、並行して流通することになります。
日本銀行から金融機関への支払いは新500円玉で行われ、徐々に新硬貨の流通量が増えていきますが、国民の手元にある旧硬貨がすぐに回収されるわけではありません。
ただし、非常に古い初代500円玉(昭和57年発行の白銅貨)については、現在では流通量がかなり少なくなっており、自動販売機など一部の機器では対応していない可能性があります。
しかし、対面での支払いであれば、初代500円玉も法的には有効な通貨です。
結論として、コンビニで旧500円玉(特に2代目)を使うことに全く問題はありません。
安心して利用できます。

令和3年の旧500円玉はレア?
「令和3年銘の旧500円玉(ニッケル黄銅貨)」は存在しますが、現時点(2024年8月時点の情報に基づく)で特に「レア」と言えるほどの希少価値があるとは断定しにくい状況です。
令和3年(2021年)は、500円玉にとって特別な年でした。
この年には、11月1日から新500円玉(バイカラー・クラッド貨)の製造・発行が開始されましたが、それ以前の期間には、従来の旧500円玉(2代目・ニッケル黄銅貨)も引き続き製造されていました。
そのため、「令和3年」という年銘が刻まれた旧500円玉が存在するのです。
新旧デザインの切り替え年にあたるため、他の年号の旧500円玉に比べると、製造期間が短かった可能性はあります。
しかし、令和3年度全体での500円硬貨の発行枚数(新旧合わせた計画)は2億枚とされており、そのうちどれだけの枚数が「令和3年銘の旧500円玉」として製造されたかは公表されていませんが、極端に少ない枚数ではないと考えられます。
貨幣の希少価値は、発行枚数の少なさ、現存数の少なさ、デザインのエラー、歴史的な背景など、様々な要因によって決まります。
令和3年銘の旧500円玉は、確かに新旧切り替え年の硬貨という点では興味深いですが、発行枚数が極端に少ないわけではなく、現在も流通している可能性が高いことから、古銭市場などで高値で取引されるような「レアコイン」とは現時点では言えないでしょう。
ただし、将来的に流通量が減少し、収集家の間で注目される可能性はゼロではありません。
もし手元にあれば、記念として保管しておくのは面白いかもしれません。
500円玉 の 新旧 の 違い まとめ
次のように記事の内容をまとめました。
- 新500円玉は中央が銀色、外周が金色の2色(バイカラー)である
- 旧500円玉(2代目)は全体が単色(ニッケル黄銅)である
- 新500円玉の側面は不規則な「異形斜めギザ」である
- 旧500円玉(2代目)の側面は均一な「斜めギザ」である
- 新500円玉には縁に微細文字(JAPAN, 500YEN)が刻まれている
- 新旧で潜像のデザインが異なる(新:JAPAN/500YEN、旧:500円)
- 初代500円玉は昭和57年(1982年)に発行された
- 2代目500円玉は平成12年(2000年)に発行された
- 最新の3代目500円玉は令和3年(2021年)に発行された
- 重さは世代ごとにわずかに異なる(初代約7.2g、2代目約7.0g、3代目約7.1g)
- 初代の素材は白銅、2代目はニッケル黄銅である
- 最新の3代目はバイカラー・クラッド構造(3種の金属)である
- 表面(桐)・裏面(竹・橘)の基本デザインは歴代で共通である
- 偽造防止技術は世代ごとに高度化している
- 新500円玉は一部の自動販売機などで使えない場合がある
- 旧500円玉(特に2代目)は現在も有効な法定通貨で広く利用可能である